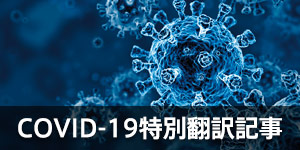先進国で進む少子化、「真の理由」は分かったのか?
2018年2月
15年たった現在、合計特殊出生率(出生率)低下の「真の理由」に迫ることはできたのだろうか。そして、先進国の少子化に歯止めをかける方策は見つかったのだろうか?

2004年12月号「落ち込む出生率の謎」によれば、日本の人口が現在のペースで減少すれば、22世紀中頃にはゼロになる。「ゼロ」というのは机上の話だが、高齢者の増加により年金や健康保険制度が崩壊し、経済的な混乱が起きるという話には現実味がある。しかもこの問題は、日本に限ったことではない。2004年の国連の報告書によれば、女性1人当たり2人の子ども(国の人口維持に必要な数)を産んでいる国は、先進国では4カ国だけだったのだ。
「先進国全体で出生率が落ち込みつつある。これは単なる社会現象なのだろうか。それとも生物としての生殖能力低下を意味するものなのだろうか。真の理由はまだ分からない。だからこそ心配だ」と、この記事の執筆者Declan Butlerは投げ掛けている。
先進国でヒトの繁殖力が落ちている理由を生物学的に探るには、ヒトの生殖細胞や初期胚が必要だ。しかし、こうした細胞を使う研究は難しかった。ヒトになり得る細胞を扱うという倫理的な問題もあるが、研究に必要なヒト生殖細胞をin vitroで大量に作り出す方法も、ヒト初期胚を体外で長期にわたり培養する方法も、分かっていなかったからだ。
どんな細胞にも分化できる「胚性幹(ES)細胞」は、ヒトでは1998年に樹立されている。ただし、1人の人間になり得る初期胚を破壊して内部細胞塊を取り出すことから「道徳に反する」との論調が今も強い。米国ではこの分野の研究助成に対する方針が時の政権により大きく変わり、欧州連合内では樹立を全く禁ずる国と、生殖補助医療用に体外受精させた(廃棄予定の)余剰受精卵からなら樹立が認められる国が存在する。他にも、ヒトES細胞を使った研究が実施できても、生殖細胞の作製が実質的に不可能な国もある。ヒト多能性幹細胞を研究に用いることは、簡単ではなかった。
新しい多能性幹細胞の登場
こうした状況に変化をもたらしたのが、人工多能性幹(iPS)細胞だ。2006年、マウスの体細胞に特定の4つの遺伝子を強制的に発現させると、多能性を持つ幹細胞様の細胞になることが報告され、さらに翌年には、ヒト細胞用のプロトコルが報告された。iPS細胞は体細胞から作ることができ、個人情報や提供に関して同意を得た上で研究が進められる。ヒトES細胞研究に立ちはだかっていた壁のいくつかが取り払われただけでなく、ES細胞で培われた知識や技術も活用でき、多能性幹細胞を必要としている研究分野は大きく前進した。iPS細胞は今日では、患者由来の細胞を用いた安全性評価試験の他、移植の際に拒絶反応を回避できるという利点から、移植用の細胞シートやミニ臓器「オルガノイド」の研究が精力的に進められている。
倫理的な問題や提供者保護の問題はクリアされた。だが、ヒト多能性幹細胞を培養して生殖細胞を得ることについては道半ばだ。マウスの多能性幹細胞から卵を作製する手法が報告されたのは2012年。この成果を報告した京都大学の研究チームは、2011年に精子の作製にも成功していた。これで、マウスでは精子も卵もそろったわけだが、この時点では、卵を成熟させるために卵巣に移植する必要があった。この問題を解決する方法、つまり、全てを体外で完結できる培養系が開発されたのは2016年である。一方、イスラエルと英国の共同研究チームは、2012年に発表されたマウスのレシピを元に、ヒト幹細胞から生殖細胞の前駆細胞を作製する方法を2014年に編み出している。従って、遠くないうちに、ヒトでもこのような培養系が確立されると予想される(2018年2月、低確率ながらも体外で成熟させる手法が報告された)。
ヒトの発生過程の問題を見つけるには、生殖細胞だけでなく、ヒト初期胚を体外で培養する方法も必要だ。これまでの最高記録は「体外で受精後9日目まで」。2016年、それを超えて、受精後13日目まで培養できる手法が報告された(受精後14日を越えて培養してはいけないという国際的な指針に従って、廃棄された)。この研究を率いたAli Brivanlou氏は、「21世紀になったのに、我々自身の発生よりも魚やマウス、カエルの発生の方がよく分かっているなんて、正直情けない気持ちです」と語っている。
ヒトの生殖・発生を細胞レベルで調べるためのツールはそろってきた。不妊や不育症の原因を探ることや、化学物質の影響を評価できるようにもなるだろう。だが、倫理問題はさらに難しいものとなる。世界各国には早急な法整備が求められており、各国が足並みをそろえる必要があるが、それはいつ実現するのだろうか。ヒト個体に発生し得る細胞を扱う研究を、十分な規制なしに進めて良いとは思えない。
出産・育児・仕事
生物学的な研究はこれからだが、ヒトを取り巻く「社会」から、手掛かりを得られないだろうか。Natureは2013年、30代の女性研究者4人に「女性であることは研究にどんな影響を与えたか?」と尋ねた。皆、出産・育児と研究生活の両立に不安を感じていたものの、「研究をあきらめるわけにはいかない」という強い意志と、職場の理解によって、それを迎え撃とうという気持ちを維持していた。秀でた成果を残している彼女たちですら不安なのだから、多くの女性はもっと不安なはずだ。女性が出産をあきらめなくて済むような仕組みが現在も十分に整っていないことを物語っていると感じる。
英国の大学では2005年から、男女共同参画を格付けするプログラムの「自主的な」導入が始まっている。ある大学では導入から3年で、教授のポストに昇進する女性の割合が28%から50%に増加した。女性の社会進出と出生率との関連は明らかではないが、同国の出生率は2003年頃から回復傾向にあり、1.63人(2002年)から1.8人(2015年)となっている(出展: The World Bank)。
人口が減少傾向にある国で、それはすぐに増やせるものではない。事実、15年たった現在も、状況はほとんど変わっていない。社会の破たんを回避するために各国取り組んでいるのに状況が変わらないということは、何か重要なことを見落としているのかもしれない。自然には未知のことが多く、生物学的研究で原因を探り、対策を見つけるには時間がかかる。一方の社会は、私たち自身が作っているものである。社会を精密に探ることで、社会的な手立ての他、ヒトの生殖に影響を及ぼしている因子についても新たな手掛かりが得られる可能性がある。自然科学と社会科学の垣根を越えた学際的な研究により、答えが導びかれることを期待する。