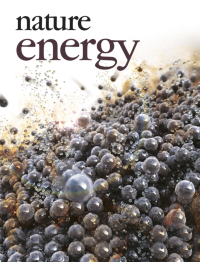酸素発生能の寿命を50倍以上に伸ばす光触媒シート開発 - 成功の秘訣は助触媒の自己再生機能 人工光合成実現に一歩先進
况 永波、山田 太郎、堂免 一成
2017年1月号掲載
太陽エネルギーを利用して水を分解し、長時間、効率よく酸素を発生させる光触媒シートの開発に、NEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)と東京大学、東京理科大学のグループが成功した。従来20時間程度にとどまっていたシートの酸素発生寿命を1100時間以上に飛躍的に伸ばし、将来の人工光合成の社会実現に道を開く成果だ。短寿命につながるシート表面の劣化を克服し、自己再生機能を持たせたのが特長で、Nature Energy 2017年1月号に発表された。中心となって研究を進めた東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻のポスドク、况永波さん、堂免一成教授、上席研究員の山田太郎さんに開発の経緯、意義などを聞いた。

―― 今回の研究は、将来の人工光合成の実現に向けた一歩ですね。背景を簡単に説明してください。
堂免氏: 光合成は、植物が太陽エネルギーを利用して二酸化炭素をもとに酸素を作り出すことです。一方、我々がめざす人工光合成は、光触媒を使い、太陽エネルギーを利用して水を酸素と水素に分解し、その水素を材料に二酸化炭素と反応させてプラスチックなどの革新的な材料を作ることです。現在、日本の化学工業は95%を石油由来のナフサに依存しているわけですが、人工光合成は化石燃料に依存せず、地球温暖化の元凶といわれる二酸化炭素の抑制につがるものです。水素は、燃料電池などに使われ、燃えても水になるので、環境にやさしいエネルギー源として、今、注目されています。
太陽エネルギーで水が分解できることは、ここ東京大学で1970年代初めに見つかっています。当時、教授の本多健一さんと、大学院生だった藤島昭さんの「本多・藤島効果」です。これは酸化チタン電極を陽極、白金を陰極として水中に浸すと、電極間に電流が流れ、水素、酸素ができるというものです。ただし、効率は極めてよくありませんでした。
私はもともと太陽光、特に紫外線を利用して水を分解する光触媒の粉末の研究を1980年ごろから始めました。当時の光触媒はチタン酸ストロンチウム(SrTiO3)。光量子の変換効率は0.1%程度しかありませんでした。現在は、エネルギーの高い紫外線域だけでなく、可視光領域にも反応する素材開発が世界中で進んでいます。
こうした流れの中で日本では、国家プロジェクトとしてNEDOが中心(当初は経済産業省)となり、産学官連携の「人工光合成化学プロセス技術研究組合」(略称ARPChem;アープケム)が2012年に発足しました。国際石油開発帝石(株)、住友化学(株)、TOTO(株)、(一財)ファインセラミックスセンター、富士フイルム(株)、三井化学(株)、三菱化学(株)の企業のほか、東京大学、東京理科大学、京都大学などが参画しています。2021年度末までに、①光触媒による水の分解で、水素と酸素を製造する、②分離膜を用いて水素を分離する、③合成触媒を用いて、水素と二酸化炭素から化学品原料となるC2〜C4のオレフィン*の製造プロセスを確立する――ことを目標に、化石燃料から脱却をめざしています。年間約15億円の予算が投じられており、私は①の光触媒素材開発のチームリーダーを務めています。

- ①光触媒開発
- 太陽エネルギーを利用した水分解で水素と酸素を製造する光触媒材料およびモジュールの開発
- ②分離膜開発
- 光触媒から発生した水素と酸素の混合気体から水素を分離する分離膜およびモジュールの開発
- ③合成触媒開発
- 水から製造する水素と発電所や工場などから排出する二酸化炭素を原料としてC2~C4オレフィンの有用な基幹化学品を合成する触媒およびプロセス技術の開発
―― 可視光領域での光触媒はいくつも見つかっているのですか?
山田氏: 私は、ARPChemの発足後、堂免教授と共に光触媒素材開発にかかわっています。これまで光触媒シートとして有望な物質はいくつも見つかっており、1つの物質で水素と酸素を効率よく発生させるもの、水素をよく発生させる物質、酸素を効率よく発生させる物質の開発という3つの観点から研究が進められています。我々東大グループでは、それぞれ3種類、5〜6種、5〜6種類ほど扱っています。今回は、酸素を効率よく発生させるバナジン酸ビスマス(BiVO4)を使った研究です。バナジン酸ビスマスは、もともとは、東京理科大学教授の工藤昭彦さんが、可視光線下で酸素を発生することを確認した物質です。可視光領域(380〜780nm)の520nm以下の波長の光(緑色)に強く反応します。我々は、この物質にモリブデンをドーピング(少量添加する)させたものに焦点を当て、酸素発生能の向上をめざしました。
―― 今回、どのようにして光触媒シートを作製したのですか?
况氏: 水に浸して反応させる光触媒の表面には、水素や酸素の発生を促進させる「助触媒」という物質を固定化するのが一般的です。これがないと光触媒は活性になりません。水素発生には、白金やロジウムなどの貴金属、酸素発生には鉄、ニッケル、コバルトなどの酸化物が用いられます。太陽光によって光触媒の中に生じた、電子と正孔のやりとりする仲介役となるわけです。通常は、光触媒の表面に、厚さ数十nmの薄膜を作るか、微粒子としてスパッタ法(真空下で、物質を蒸着させる薄膜製造の一手法)で固定化させますが、これが水分解する過程ではげ落ちてしまうため、すぐに光触媒の寿命を迎えてしまうという欠点がありました。
そこで、光触媒を工夫し、助触媒が常に表面に固定させる方法はできないかと考え、ニッケルなどの助触媒を作る材料の供給源に注目しました。バナジン酸ビスマスの粉末をガラス基板上に塗り、その上に導電層としてニッケルとスズを二層になるよう蒸着させたのです。それを裏返し、酸素発生能を有する光触媒シートを開発しました。粒子転写法という手法です(図2)。

―― このシートの特長は?
山田氏: シートは、光触媒のバナジン酸ビスマス粒子がスズとニッケルの薄膜に強固に接合されています。これをごく微量の鉄イオン(Fe2+)がある水溶液に入れると、ニッケルイオン(Ni2+)が微量溶け出し、鉄イオンと結合して鉄ニッケル混合酸化物(NiFeOX)が形成されます。これがバナジン酸ビスマスの表面に固着し、持続的な光触媒の助触媒になることを見いだしました(図3)。

(a)光触媒シートを鉄イオンが混じった水溶液に入れると、(b)導電層のニッケルイオンが溶けだし、(c)鉄ニッケル酸化物となる。助触媒としてバナジン酸ビスマスの表面に固定化される。助触媒が劣化しても次々に助触媒が生成され、自己複製される。 | 拡大する
―― 持続的に助触媒が作られることで、光触媒シートの酸素発生能が高まった?
况氏: そのとおりです。今回の研究は、アノード(陽電極)に光触媒シートを使い、酸素発生能の向上をめざしたものです。カソード(陰電極)には白金を使い、0.4V程度の低電圧を両極にかけますが、太陽光エネルギーがないと光電流は流れず、酸素も発生しません。光照射によって光電流が流れ、その結果としてどのくらい酸素発生能が持続するかを調べました。その指標が、光エネルギーを照射した時の光電流の安定性です。従来の手法で助触媒を固定化したバナジン酸ビスマスの光触媒と、我々の手法で開発した触媒シートの光電流を測定し、比較しました。
―― 結果はいかがでしたか。

新たな手法の光触媒シートは、1100時間を経過しても電流の活性が変化せず安定している。従来法は、20時間で劣化し、活性が失われた。(縦軸・光電流の密度、横軸・時間) | 拡大する
况氏: 我々の手法で作成した光触媒シートは、1100時間(約46日)を経過しても電流発生の活性に低下が見られないことが確認されました。一方で、従来法は、20時間ほどで活性が低下していきました。我々の方法では、シート表面にある助触媒の鉄ニッケル混合酸化物(NiFeOX)が脱落や溶解しても、導電層であるニッケル層からNi2+が微量に溶出して、助触媒が自己再生されているからです。助触媒が常に供給されるため、酸素発生能力が従来法の50倍以上持続可能となったのです。

シートからニッケルが溶けだし、鉄イオンと結びついて酸化物となり、シート表面に供給される。 | 拡大する
―― 自己再生というのは興味深いですね。
况氏: こういう光触媒は、初めてです。ここまで光触媒の寿命を伸ばす新たなメカニズムを示したという意味でも、画期的な成果だと思います。
―― 光エネルギーの変換効率はどのくらいでしょうか、また今後の見通しは?
堂免氏: 今回の酸素発生する光触媒シートのエネルギー変換効率は、1.6%を超える程度です。我々のプロジェクトチームでは、さらに、酸素発生用にバナジン酸ビスマス、水素発生用にCIGS(銅・インジウム・ガリウム・セレン)の光触媒シートを重ね合わせ、光エネルギーを2段階で利用できるタンデム構造の光酸水素発生装置を作りました。これにより最高3%の変換効率を達しています。これは植物の光合成の約10倍の効率ですが、太陽光発電などに比べると、まだまだ低い。これを2021年度末のプロジェクト終了までに10%程度に引き上げるのが目標です。理論的には50%まで可能です。
―― 况さんは今後どうされますか?
况氏: 4月に中国の浙江省にある中国科学院寧波材料技術与工研究所(寧波材料研究所)に戻り、引き続き光触媒の研究を続けます。日本に負けないよう研究を続けていきます。
―― ありがとうございました。
聞き手は、玉村治(科学ジャーナリスト)。
*オレフィンは二重結合を持つ炭化水素化合物。C2がエチレン、C3はプロピレン、C4はブテンで、プラスチックの原料となる。
Nature Energy 掲載論文
Article: 動作中自己再生機能による高安定・耐光腐食性・低バイアス動作の水分解用光アノード
Nature Energy 2 : 16191 doi:10.1038/nenergy.2016.191 | Published online 19 December 2016
Author Profile
堂免 一成(どうめん かずなり)
東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻 教授
| 1976年 | 東京大学理学部化学科卒業 |
| 1976年 | 東京大学宇宙航空技術研究所研究生 |
| 1982年 | 東京大学理学系大学院理学系化学専門課程博士課程修了(理学博士) |
| 1982年 | 東京工業大学資源化学研究所(現、化学生命科学研究所)触媒化学部門 助手 |
| 1990年 | 東京工業大学資源化学研究所基礎測定部門 助教授 |
| 1994年 | 東京工業大学資源化学研究所触媒化学部門 助教授 |
| 1996年 | 東京工業大学資源化学研究所触媒化学部門 教授 |
| 2004年 | 東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻 教授(現職) |

山田 太郎(やまだ たろう)
東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻 上席研究員
| 1979年 | 東京大学理学部化学科卒業 |
| 1982年 | 米国スタンフォード大学化学工学科留学(フルブライトプログラム)(〜83年) |
| 1984年 | 東京大学理学系大学院理学系化学専門課程博士課程修了(理学博士) |
| 1984年 | 東京大学物性研究所極限物性部門 助手 |
| 1990年 | 米国IBMアルマデン研究所 客員研究員 |
| 1993年 | 科学技術振興事業団 固液界面プロジェクト グループリーダー、技術参事 |
| 1998年 | 早稲田大学各務記念材料技術研究所 助教授 |
| 2001年 | 理化学研究所表面化学研究室 協力研究員 |
| 2003年 | 理化学研究所表面化学研究室 専任研究員 |
| 2013年 | 東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻 上席研究員(現職) |

况 永波(Yongbo Kuang、かん よんぼ)
東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻 特任研究員
| 2007年 | 中国上海交通大学化学化工学院応用化学卒業 |
| 2011年 | 東京工業大学大学院理工学研究科有機・高分子物質専攻博士課程修了(博士(工学)) |
| 2011年 | 東京工業大学大学院理工学研究科有機・高分子物質専攻 産学官連携研究員 |
| 2013年 | 東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻 特任研究員(現職) |