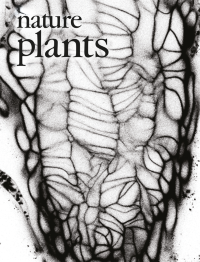非自己を認識する自家不和合性の仕組みを、理論的にも検証!
藤井 壮太
2016年9月号掲載
2015年のNature Plants 創刊号で、ペチュニアが自己の花粉と非自己の花粉を識別し、他者の花粉だけを受け入れる「非自己認識の仕組み」について発表した、奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科の高山誠司教授(現東京大学農学生命科学研究科)、久保健一研究員らのチーム。今回、新たに藤井壮太氏がこれまでに解明した仕組みを理論的に検証。3人のコラボレーションにより、非自己認識システムがより強固にそして確実に証明された。
―― 今回、高山教授、久保氏とともに、新しい成果を加えて自家不和合性についての総説として発表されました。

雌しべの先端に非自己の花粉が付くと、吸水・発芽して、花粉管が胚珠にまで伸びていく。花粉の精細胞が花粉管を通り、胚珠の卵細胞と受精し、やがて種子ができる。 | 拡大する
藤井氏: 植物の受精は、雌しべに雄しべ由来の花粉が付いた後、そこから管(花粉管)が伸び、花粉の精細胞が胚珠の卵細胞と出会うことで成立します。このとき、約半数の植物では、自己の花粉を排除する自家不和合性が働きます。近親交配が起きると遺伝的な多様性が失われ、種は生存の危機にさらされるからです。こうした自家不和合性には、「自己を認識して、それを排除する」自己認識タイプと、「非自己を認識して、それを受け入れる」非自己認識タイプがあります。例えば、アブラナ科は前者、ナス科やバラ科は後者であることが知られています。非自己認識タイプの分子メカニズムは、なかなか解明が進まなかったのですが、高山先生と久保さんが研究を進め成果を挙げてきました。今回、その成果について理論的検証を行い、総説としてまとめました。
―― 自己認識タイプの仕組みはわかっていたのですか?

アブラナ科は自己の花粉の表層物質(SP11/SCR)と雌しべのSRKが直接結合し、分子認識と花粉の拒絶が起きる。一方、ナス科では、非自己の雌しべのS-RNase(毒)と花粉SLF(解毒剤)が直接結合し、分子認識によって花粉が受け入れられる。 | 拡大する
藤井氏: 自家不和合性はダーウィンが発見したとされています。その後、かなり前に、S遺伝子という遺伝子の働きによって自己と非自己を識別されることが明らかにされていました。例えばアブラナ科植物では、S遺伝子に「塩基配列の異なるバリエーション(S1、S2……Sn:ハプロタイプという)」が何種類も存在し、「雌しべのSタンパク質」と「花粉のSタンパク質」が同じハプロタイプだと「自己」と認識されることが突き止められました。両者が結合すると花粉を排除するシグナルが発せられ、受精が成立しない仕組みになっていたのです1。機能する分子は異なりますが、ケシ科でも同様のメカニズムが用いられていると考えられています。
―― 今回は非自己認識タイプの理論的検証をされました。
藤井氏: 非自己認識タイプはすんなり受け入れられませんでした。今回の成果は、実験によって証明されて認められるようになり、理論を検証できる段階になったことが大きかったと思います。というのも、高山先生と久保さんは、2003年よりナス科のペチュニアを用いて「非自己を認識し、非自己の花粉だけを受け入れる」との仮説を立てて研究を進めたのですが、はじめはなかなか認められなかったのです。
その後2010年に、久保さんをはじめとする高山先生の研究チームは、非自己認識タイプでは、S遺伝子座から「自己の花粉を殺す毒として機能するRNA分解酵素(S-RNase)」と、「非自己の毒を無毒化できる解毒剤(F-box因子:SLF)」が作られることを実験で示し2、状況が変わってきました。1つの花粉のS遺伝子座には少しずつ異なるタンパク質が複数並んでコードされており、S-RNaseもSLFも10種類存在することを示し、そのうえで「どの解毒剤がどの毒を解毒するか」、つまり「種子ができるか否か」を、複数の組み合わせで検証したのです。
さらに久保さんが徹底した検証を行ってNature Plants の創刊号(2015年1月)で発表し 3、非自己認識の仕組みが受け入れられるようになりました。ほぼ同時期、シュプリンガーネイチャーより高山先生に、同じくNature Plants に「最近の自家不和合性研究の進歩について総説を書けないか」との打診がありました。そこで3人で相談し、「証明は強固だし、パラダイムシフト的におもしろい現象だが、まだまだ考え方が世に浸透していない(と自分たちでは感じている)非自己認識をトピックにしよう」ということになりました。さらに高山先生が「理論モデル作ろう」というハードルまで作ってくださいましたので、私が技術者として非自己認識をモデルとしてシミュレーションで検証することになったのです。
―― ゲノム情報からは、自己認識か、非自己認識かわからないのですか?
藤井氏: 残念ながら、ゲノム情報から区別することは極めて難しいです。現時点では、実験による詳細な機能解析が必要になります。例えば、同じ非自己認識タイプのナス科とバラ科は、進化の系統からみると遠い存在です。おそらく、両者の共通祖先がすでに非自己認識の仕組みを持っていたと考えられ、その後アブラナ科などに見られる自己認識タイプが出てきたと推測されています。アブラナ科の自己認識は、病原体を認識する仕組みを由来とするのではないかとされていますが、まだ検証されていません。現時点で言えるのは、自家不和合性の仕組みは進化の過程で何度も並行してターンオーバーしていますが、非自己認識がデフォルトであったのではないかということです。
―― これまで、モデルやシミュレーションによる研究もされていたのですか?
藤井氏: いいえ、今回が初めての経験で、Javaの教本を片手に行いました。私は実験生物学者で、博士課程までは自家不和合性ではなく花粉形成をテーマにしていました。その後、花粉形成に関与するミトコンドリア、ミトコンドリアに関連する葉緑体など、生殖、進化、分子の相互作用をキーワードに研究を行ってきましたが、2014年に奈良先端科学技術大学院大学(NAIST)に赴任してから自家不和合性の研究を始めました。同時に、解明した分子メカニズムの意義を追求するにはモデルを立ててシミュレーションするのがよいと考えるようになり、実験に加え理論研究も行うようになりました。
ただし、私自身の実験では主にシロイヌナズナを用いており、ペチュニアは扱ったことはありません。シミュレーションは「現実をよく観察すること」が大切だと思いますが、これではスタートラインに立てません。一方、久保さんはペチュニアのコレクターで、徹底的に集めて調べ上げており、非自己認識について世界で最もよく知る人物です。今回のシミュレーションは、ペチュニアの生態から非自己認識の分子モデルまで、久保さんの大小の助言があったからこそできたといえます。
―― 具体的に、どのようなモデルを立てたのでしょう?

バーチャル植物集団は交配し、生存競争し、非自己認識による自家不和合性を維持しながら世代交代するように設定した。そのうえで、分子進化が起こり、相互作用する新しいSLFとS-RNaseが生じるまでをシミュレーションした。 | 拡大する
藤井氏: コンピューター上にペチュニア様の仮想植物集団を作り、媒介者がランダムに受粉させるフレームワークを構築しました。それぞれの個体はペチュニアと同じく、雌しべに「自己の花粉を殺すS-RNase」を、花粉に「解毒剤となるSLF」を持っており、それぞれの遺伝子にもランダムに変異が入る設定です。S-RNaseとSLFは互いに異なるハプロタイプだと非自己と認識し、受精が成立して世代交代します。このような条件の下で、「新しいS-RNase」と「新しいSLF」を持つ個体が1つずつ出現し、一定期間のシミュレーション内でそれぞれが互いを認識して集団内で共存できる、つまり、変異遺伝子が集団で安定して存在するようになるまでを評価しました。そのうえで、「新しいS-RNaseと新しいSLFはどちらが先に出てくるのか」といったことも検討しました。
実はこのテーマについては、2000年に、実験生物学者と理論学者が激しい議論を交わした経緯があるのですが4−6、残念ながらこのときは皆、自己認識システムを想定していました。今回、同じ議論を再燃させるべく、本当の分子メカニズムである非自己認識システムを前提でモデルを立てました。
―― どのようなことがわかったのでしょう?
藤井氏: 順調なら1週間で十分なシミュレーションですが、プログラムを修正しつつ走らせたので長い時間がかかりました。何度も試行錯誤を繰り返してやっと理論どおりの「新たなS-RNaseとSLFのペア」が出現し、仮想植物集団内に安定して存在するようになりました。このことは、高山先生と久保さんが実験で明らかにした非自己認識の仕組みが、現実世界でも安定して存在可能なことを支持しています。

新しいSLFは緩衝力が働くため、先に集団に広まることができる。続いて、新しいS-RNaseが進化すると、それに対して解毒作用を持つ新しいSLFは有利になるため、急激に集団中に広まることになる。 | 拡大する
興味深いことに、まず解毒剤となるSLF側に新しいものが出現し、その後で新しいS-RNaseが進化してくることもわかりました。通常、ウイルスなどの外部からの異物に対しては、侵入後に抗体が作られると考えがちで、感覚的には受け入れがたい気もします。が、この場合、「解毒剤がすでに存在するから、安心して毒を投与できる」というシステムなのです。SLFには10〜20の遺伝子パターンがあり、複数のSLFが同じS-RNaseを認識できる場合もあることがわかっています。つまり、冗長的なSLFが多少増減してもたいした影響がないといえ、この「緩衝力」が進化を推し進める原動力になったと解釈できます。これに対し、S-RNaseで新しいものができて解毒因子がないままだと、その個体は受精不可能な状態に陥り、やがて集団から排除されていくと考えられます。まずSLFが進化して新たなものが出現するほうがリーズナブルだといえるのです。
―― さらなる謎や解析すべき点はありますか?
藤井氏: 実験と理論で非自己認識の仕組みを検証できたので、その確かさは実証できたと自負しています。ただし、実際の進化では最初は3種だったS遺伝子が20種に増えたと思われ、タンパク質の構造変化なども含めて、どのようにして多様化したのか、まだまだ未解明の部分が多いと思います。また、非自己認識タイプを祖先系とする植物が、アブラナ科でどのように自己認識タイプに変わったのかといったこともわかっていません。これには新しい種が誕生するプロセスも密接にかかわっています。こうした点について、複雑な現象を納得できるまで単純化していきたいと考えています。他領域や若い研究者にもどんどん参入いただきたいですね。生殖と分子進化をキーワードに、ダーウィンに挑戦したい学生も募集しています!!!
―― 非自己認識システムの研究成果は、農業などに応用できるのでしょうか?
藤井氏: 育種の世界では雑種を作る目的で自家不和合性が応用されることはありますが、一般の農業においては自家不和合性が働かないほうが都合のよい場合が多いです。ですから、自家不和合性をうまく制御することは育種学における長年の課題で、その基礎理論を理解することが重要といえます。
また、今回シミュレーションという手段を用いましたが、今後は物理環境をパラメーターとして組み込むことを視野に入れています。例えば、「温暖化に先がけて、自家不和合性がどのような影響を受けるのか」といったことを理解する足場ができると考えています。
さらに、個人的におもしろいだろうと思っているのは、非自己認識のような仕組みをヒントにして新しいアルゴリズムが生まれることです。私は今後も理論と分子メカニズムの解明に努めたいと思っており、多方面に応用が広がることを期待しています。
―― 最後に、Nature Plants とのやりとりは順調だったのでしょうか?
藤井氏: 非常に苦労しました。最初の投稿は2015年の9月でしたが、査読者4人から進化理論部分について77もの指摘を受けました。自分の経験では、これまでで最も過酷な査読になりました。「理論の専門家は議論好き」というのがあるのかもしれませんが、一つ一つ修正していくのは骨が折れました。何度もシミュレーションをやり直して10か月後の2016年4月に再投稿し、予定より大幅に遅れて受理されました。草案から掲載までは2年近くかかったと思います。そのかいあって「授業で教材として使います」と言ってくれている専門家もおり、うれしく思っています。
―― ありがとうございました。
聞き手 西村尚子(サイエンスライター)。
参考文献
- Takayama S., et al. Nature 413, 534-538 (2001).
- Kubo K., et al. Science 330, 796-799 (2010).
- Kubo K., et al. Nature Plants 1, 14005 (2015)
- Charlesworth D. Plant Cell 12, 309-310 (2000).
- Uyenoyama M., Newbigin E. Plant Cell 12, 310-312 (2000).
- Matton D., et al. Plant Cell 12, 313-315 (2000).
Nature Plants 掲載論文
Review Article: 植物の自家不和合性の非自己および自己認識モデル
Non-self- and self-recognition models in plant self-incompatibility
Nature Plants 2 : 16130 doi:10.1038/nplants.2016.130 | Published online 6 September 2016
Author Profile
藤井 壮太
奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科 細胞間情報学研究室 助教(現職)
| 2009年 | 東北大学大学院農学研究科博士課程修了(博士(農学)) |
| 2009年 | University of Western Australia, Research Associate |
| 2011年 | 京都大学大学院理学研究科 日本学術振興会特別研究員SPD |
| 2014年 | 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科 細胞間情報学研究室 助教(現職) |
| 2016年 | 科学技術振興機構さきがけ研究者(兼任) |