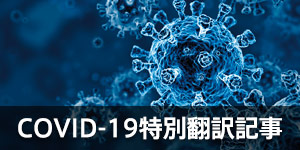レアメタルを使わない第3世代の有機EL発光材料開発の成功 ― 低コストで、100%の内部量子効率を達成
魚山 大樹氏
2012年12月13日掲載
電気を通すと有機化合物がきれいに発光する「有機EL(Electroluminescence)」。消費電力の少ない、次世代のディスプレイ、パネル素材として注目されているが、魚山さんは、世界をリードする安達千波矢(あだち・ちはや)(九州大学大学院教授・OPERA所長)の指導の下、第3世代と呼ばれる、低コストの有機EL用新発光材料の開発に成功した。イリジウムなどレアメタルを使わずに、電気を光子に変換する効率(内部量子効率)をほぼ100%まで高めたのが特徴で、実用化への期待が高まっている。成果は、Nature 2012年12月13日号に掲載された。魚山さんは「自分では思いつかない発想の異分野の研究者の触れ、多くのライバルと切磋琢磨する環境が良かった」と、内閣府の最先端研究開発支援プログラム(FIRST)の支援を受けるOPERAの研究環境の良さが、世界の注目を集める成果につながったことを強調した。
―― 今回の成果は第3世代の素材開発ということですが、まずは有機ELの仕組み、歴史を簡単に説明してください。
魚山氏: 有機ELが光る原理は、電気などによって、有機化合物が安定した「基底状態」からエネルギーの高い、不安定な「励起状態」に移る現象が関係しています。有機物はもとの安定した状態に戻る際、光などとしてエネルギーが放出されます。この光が有機ELの光です。光以外にも熱として放出されることがありますが、電気が100%光子に変換されれば、熱は発生しません。
基底状態から励起状態になるのは、有機物の中で、電荷の「再結合」が起きているからです。有機ELの基本構造は、有機物(材料)を電極ではさみこんでありますが、陽極付近では有機分子から電子が奪われ(酸化され)、ホール(正孔)ができます。陰極では電子が与えられ(還元され)、このホールと電子が、有機材料の中を対極電極に向かって動き、やがて結合します。これが再結合です。どんな材料がこの再結合が起こりやすく、そして光への変換効率がいいのか、それを見つけたり、開発したりするのが有機ELの発光材料の研究です。
有機ELとして最初に報告されたのは、1953年。フランスの研究者が、植物の細胞壁、繊維の主成分であるセルロースにアクリジンオレンジをドープして電流を流すと、蛍光発光することを突き止めました。1965年には、ベンゼン環が3つ連なったアントラセンが有機ELになることがわかりましたが、いずれも電流から光子への内部量子効率は極めて低かったのです。その後、有機EL研究は低迷し、苦難の時代が続きました。
その突破口となったのが、1987年にアメリカの研究者によって発表された有機ELです。現在の有機ELの基本型である積層構造で、有機EL素子は、発光層と電子輸送層にアルミキノリノール錯体、正孔輸送層に芳香族ジアミンを用いて、わずか10Vの電圧で外部量子効率1%を達成しました。ただ、まだ効率は低かったのです。
―― それを改良したのが、第2世代なのですね
魚山氏: 有機ELの発光には、蛍光(fluorescence)と、りん光(燐光、phosphorescence)の2種類があります。有機ELの研究当初から用いられた第1世代の「蛍光材料」は、身近なところにもある有機材料です。例えば、洗剤の成分に含まれる蛍光増白剤です。蛍光材料は、比較的容易に合成でき、種類が豊富で、コストがかからないという利点があります。しかし、有機ELした場合、発光効率が低いというデメリットがあります。第2世代のりん光材料は、蛍光材料より高い発光効率が期待できると予想されていましたが、りん光は常温では発光しないというのが、1990年代中頃までの常識でした。ところが世界的な研究が進み、1997年から、プリンストン大、南カリフォルニア大などの研究チームは、レアメタルを含む有機材料で、常温でのりん光を発光させること成功しました。この研究にはプリンストン大に留学中の安達先生も関わっていました。その後、イリジウムを用いた材料で内部量子効率も100%を達成し、もう研究は終わり、勝負ありと思われていました。
しかし、りん光材料は、レアメタルを含む錯体化合物なので材料設計に制限が多く、安定性にも問題がありました。レアメタルはとても高価であるため、安達先生は、低コストの第1世代、高い変換効率の第2世代を合わせ持った第3世代の新材料の開発に取り組んできたのです。注目したのは、「熱活性化遅延蛍光(TADF)」材料というものです。約10年間、分子設計の改良を重ね、今回開発したカルバゾリルジシアノベンゼン誘導体(CDCB)という非常に簡単な構造の材料が、内部量子効率がほぼ100%のTADF材料だったのです。レアメタルを使わない新しい材料で、コストは第2世代の10分の1になります。
―― 熱活性化遅延蛍光というのは難しい名前ですが、どんなものか説明してください。
魚山氏: その前に、有機ELの発光現象の蛍光とりん光の仕組みから説明しましょう。
電気を流すと再結合によって、有機EL材料は不安定な励起状態になりますが、この励起状態にも実は2種類あることが知られています。エネルギーが高い「一重項励起状態」と、エネルギーが低い「三重項励起状態」です。
一重項励起状態、三重励起状態というのは、基底状態から励起状態になる電子のスピンの向きで決まります。スピンには、磁石のS極、N極のように、「上向き」「下向き」があります。基底状態では、スピンは上向きと下向きがペアになって存在しています。一重項励起状態というのは、元の軌道に残った電子と、励起された電子の向きが逆向きなので、不安定な状態です。このため、短時間で基底状態に戻ろうとするので、発光までの時間は短くなります。一方で、三重項励起状態は、励起された電子の向きが、元の軌道と同じ方向を向いた状態です。このため、基底状態に戻りにくく、電子がそのまま居座ろうとし、励起状態が長くなり、発光する前に分子運動によってエネルギーが消費されます。一重項励起状態と三重励起状態の間には、大きなエネルギー差があります。エネルギーは、より高い一重項励起状態から低い三重励起状態に移動することはありますが、その逆は、ほとんどありませんでした。
これが起きるのが、熱活性化遅延蛍光(TADF)です。熱エネルギーで、2つの励起状態のエネルギーギャップを乗り越え、寿命の長い励起三重項状態を経由し、発光が遅れることから、熱活性化遅延蛍光と呼ばれます。
統計学的に見ると、電荷の再結合により、有機EL材料で、蛍光となる一重項励起状態、りん光となる三重項励起状態の割合は、1対3であることがわかっています。単純な蛍光材料では、エネルギーの25%しか取り出せないことになります。我々は、三重項に移ったエネルギーを、再び一重項の励起状態に引き上げ(アップコンバージョン)て、より高効率の蛍光材料開発を目指しました。これがTADF材料です。

第3世代は、生産コスト、材料の安定性に優れた第1世代、発光効率に優れた第2世代の良い特徴を併せ持ち、実用化への期待が高まる。
―― TADF開発成功の秘訣は何だったのですか
魚山氏: 先ほども触れましたが、一重項励起状態と、三重項励起状態にはエネルギーギャップがあります。このギャップをできるだけ小さくするような材料をつくることで、いったん三重項励起状態となったものを、再び一重項励起状態に戻し、蛍光を取り出すことが可能になったのです。
これを可能にした基本原理は、教科書にも載っている波動関数でした。これをもとに、電気励起したときの電子供与する部分(HOMO=最高占有軌道)と、受け取る部分(LUMO=最低非占有軌道)の重なりができるだけ小さなるようバランス良く配すること、励起状態の構造変化を抑制することで高発光効率のTADF材料の開発が成功したのです。

一重項励起状態と三重項励起状態にはエネルギーギャップがあるが(左図)、このギャップをできるだけ小さくするよう分子設計することで、いったん三重項励起状態に移ったエネルギーを、再び一重項励起状態に戻すことで、効率の高い蛍光を取り出すことに成功(右図)。これが熱活性型遅延蛍光(TADF)である。
S0:基底状態 S1:一重項励起状態 T1:三重項励起状態 e:電子 h:ホール
―― 安達研では10年来の研究だったのですね。
魚山氏: そうです。有機ELでは電気を光に変える内部の効率が100%だったとしても、それを外部に取り出すとき(外部量子効率)は20%程度です。光が外に出てくるとき、有機EL表面のガラス板などに反射してしまうからです。安達研は2004年頃からTADF開発に乗り出し、私の先輩の研究員が何人も研究を続けていました。2009年には、ポルフィリン誘導体を用いた遅延蛍光現象を世界ではじめて確認しましたが、外部量子効率は0.1%程度と極めて低いもので、注目はあまりされなかったようです。
―― そんな状況の中で、魚山さんが安達研の門をたたいたのですね。
魚山氏: 私は愛媛大学の大学院で有機化学を専攻し、有機エレクトロニクス分野の中でも、有機材料の分子設計の奥が深い有機EL分野で力を試してみたいと思っていました。日本学術振興会特別研究員でしたので、実際に、有機EL材料を開発したいと、安達先生にお願いしました。そして、2011年4月から九州大のOPERAに移ってきました。
ちょうどその年に、安達研では、外部の発光比率が5.3%となるTADF材料を開発したと、発表しました。これは蛍光材料の発光比率の限界である5%を上回っており、明らかに遅延蛍光材料ができたことを意味します。ようやく学会などが注目するようになってきました。その後、他の研究員が10%、12.7%、14%と少しずつ効率の高いTADFを開発しました。
私が最初に取り組んだのは、産業への応用を意識した合成しやすい有機材料です。HOMO、LUMOがうまく分かれているような分子設計をし、150種類くらいシミュレーションし、実際に10種類合成し実験を重ねました。しかし、半年たってもうまくいきませんでした。安達先生に相談しながら、今回の論文になった有機材料であるカルバゾリルジシアノベンゼン誘導体(CDCB)に着目して設計し直しました。すると、このCDCBを発光層にした有機ELの外部量子効率が19.3%と極めて高いことを、比較的短期間で確認できました。2012年2月頃だったと思います。
これは電気励起で、三重項励起状態がほぼ100%一重項励起状態にアップコンバージョンし、そこからEL発光したことを意味しています。
これは有機EL研究のマイルストーンで、Nature に提稿しようと研究室内で慎重に再現実験を繰り返しました。2012年の7月に Nature に投稿し、10日後にはレフリーの査読に回ったとの連絡が入り、11月下旬にアクセプトされることが決まりました。
―― 研究成果の意味合いを教えてください。
魚山氏: これまで100%の内部量子効率(=20%の外部量子効率)は、イリジウムなどレアメタルを含有するりん光材料でないと達成できないとされていましたが、今回の成果はレアメタルを使わなくても極めて高い有機ELが実現可能であることを示しました。コストは従来の10分の1以下となり、有機ELの材料が今後、第2世代のりん光材料から、第3世代のTADF材料に大きくシフトしていくきっかけとなります。有機化合物は無限の構造を作り出すことができます。分子設計次第では、色合いがきれいなRGBなど三原色も作れるし、耐久性や耐熱性があるものも作れます。高性能で安価な有機EL実用化も夢ではありません。

設計の幅が広がり、様々な色合いが出せるようになった第3世代のTADF材料。
―― 安達研は最先端研究開発支援プログラム(FIRST)の支援を受けています。
魚山氏: 私はFIRSTの博士研究員(PD)としてではなく、日本学術振興会特別得研究員として安達研究室に約1年いました。先生は日頃から、「実際に物作りから、物性まで1人でやれ。追い込むまでやらないと見えてこない」「大学は、学問だけではなく、実用化につながる数字を出せ。ごまかしをするな」と語り、博士研究員の自主性にまかせてくれました。FIRSTのおかげで、違う業種の民間企業から研究者が集い、多くの博士研究員らがある意味、ライバルとして成果を競い合う環境です。自分は絶対発想しない考えにも触れることが多く、とても刺激的です。こうした環境だからこそ、世界をリードする研究成果がでていると思っています。
今後は企業などと連携し、実用化に向け踏み出していくことになります。

TADFを発光層に用いた有機ELのディスプレイ。
―― 最後に、有機化学に進まれた経緯、学生、若手研究者へのメッセージをお願いします。
魚山氏: 有機化学を専攻したのは、炭素、水素、窒素などシンプルな元素の組み合わせで、さまざまな機能を持つ分子を創造できるところに面白さを感じていたからです。有機EL分野に進んだ理由について、お話しましたが、単純に有機ELの発光の美しさや、今後の可能性にも魅力を感じていたからです。
研究者として歩みだしたばかりの私が言うのも恐縮ですが、まず自分のバックグラウンドとなる分野をしっかり身につけることが大事です。その上で、他の分野の研究に幅広く挑んでいくことです。自分の思いを持って、それが応用されていくのを見るのは、とても面白い。異分野の人と接しながら新たな分野を開拓していくことは、醍醐味で、とても勉強になります。現在は有機EL以外の研究をしていますが、いずれは有機ELの研究もしたいなと思っています。
―― ありがとうございました。
聞き手 長谷川 聖治(読売新聞科学部記者)。
Nature 掲載論文

Letter:遅延蛍光を利用した高効率有機発光ダイオード
Highly efficient organic light-emitting diodes from delayed fluorescence
Nature 492, 234–238 (13 December 2012) doi:10.1038/nature11687
Author Profile
魚山 大樹
| 1983年 | 愛媛県生まれ |
| 2002年 | 愛媛県立松山南高校理数科卒業 |
| 2006年 | 愛媛大学理学部物質物理学科卒業 |
| 2008年 | 同大学院理工学研究科博士前期課程修了 |
| 2011年 | 同 博士後期課程修了 |
| 2011年 | 博士号取得(理学) |
| 2010年 | 日本学術振興会特別得研究員DC(愛媛大 宇野英満研究室) |
| 2011年 | 同 PD(九州大 安達千波矢研究室) |
| 2012年 | セントラル硝子 化学研究所 |