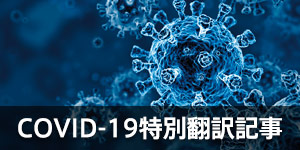混沌状態をすっきりさせるような研究が好き
長田 重一氏
長田重一大阪大学免疫学フロンティア研究センター教授は、アポトーシス(プログラム細胞死)の分子メカニズムの解明など、すばらしい業績を残してきた。いくつもの論文が引用ランキングに並ぶ。その始まりは、1980年に成功したインターフェロンα遺伝子のクローニングだった。

追試実験から発見を手にした幸運
―― 研究の世界に進んだ動機は何ですか。
長田氏: 生物学の研究をしたいと思ったきっかけは、東京大学教養学部での丸山工作(まるやまこうさく)先生(後に千葉大学学長)の講義です。DNA、RNA、セントラルドグマなど、分子の言葉で生命を語ること、それがすごく新鮮でした。
生命の謎解きに興味を持ち、ドロドロしたことをやりたいと思って、大学院では東京大学医科学研究所の上代淑人(かじろよしと)先生の研究室で生化学を習いました。
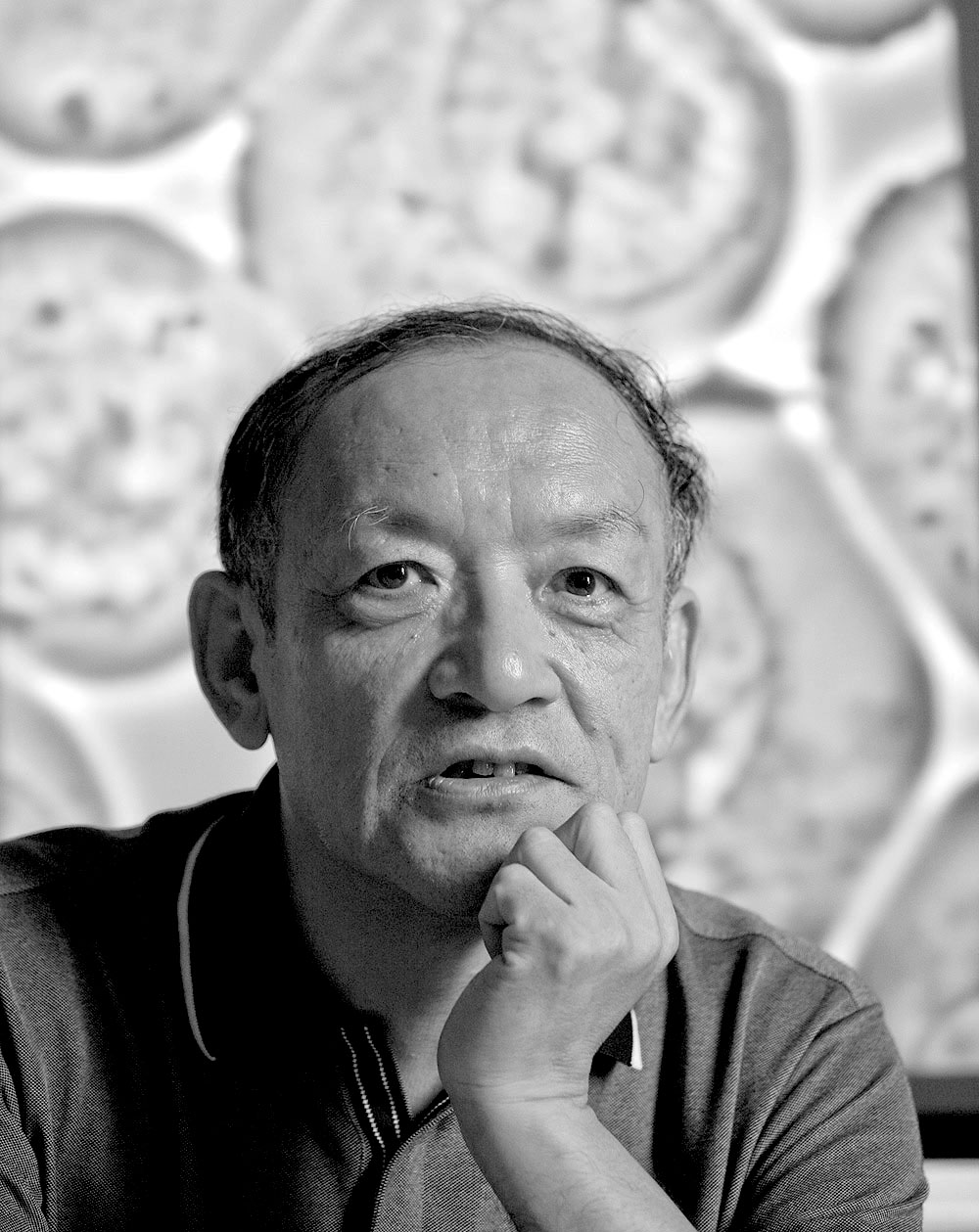
アポトーシス研究の第一人者。 | 拡大する
テーマはブタの肝臓から酵素の精製です。朝5時、品川の東京食肉市場に行って新鮮なブタの肝臓を手に入れ、医科研へ持って帰り、ホモジナイズする。米国の生化学雑誌に、「ペプチド鎖延長反応を触媒する因子EF-1をウサギの網状赤血球から精製した」と報告されました。この実験の追試です。ブタ肝臓から同じ方法を用いてEF-1を精製しようとしたのです。しかし、なかなかうまくいきません。「君は追試もできないのか」。散々でした。あるとき、この酵素がとても不安定なことに気づきました。安定化して精製すると、ウサギのEF-1とは分子量が異なるが、強い活性を持つ分子が精製されました。これこそ、本来のEF-1だったのです。米国のグループはほとんど活性を失った凝集体をウサギEF-1として報告していたのです。ずっと苦労し悩んでいたことが、ある日突然クリアになる。感動しました。それが修士2年の時。それからやみつきになりました。
―― 成功したのは腕がよかったからですか。
長田氏: 修士ですから技術なんかない。緩衝液のpHを変えてみたり、塩の濃度を変えてみたりして、酵素の安定化、精製の最適条件を探していくという作業を、毎日繰り返しました。それが偶然うまくはまったのです。
―― でも失敗する人もいるわけですよね。
長田氏: 私の恩師の一人、早石修(はやいしおさむ)先生は、「研究者には『運、鈍、根』が必要だ」と言われました。「運」をつかむためには、半端な仕事ではうまくいかない。「根」気よく続けるのが大切だと。頭がよすぎてもダメ。よすぎると「こうすればこうなる」と思ってしまう。「鈍」、バカになってやること。そのとおりだと思います。
大学院の時代、実験がうまくいかなくて泣きたくなることが多々ありました。そんな時は、バイクに乗って横浜へ行き、海を見ながら泣きました。研究者は皆同じような経験をしていると思います。
インターフェロン(IFN)のクローニングに成功
―― チューリッヒに行かれたのはいつですか。
長田氏: チューリッヒ大学(スイス)のワイスマン研究室に行ったのが77年11月。組み換えDNA技術が登場して間もない時です。この技術を用いた仕事は日本では誰もやっていない時代です。当時、私は27歳。テクニックを学んで帰れればいいかな、というくらいに考えていました。
―― なぜワイスマン先生のところに行かれたのですか。
長田氏: 「組み換えDNA技術を習えるところに留学したい」と上代先生に相談したところ、ワイスマン先生を紹介してくださいました。上代先生は、ワイスマン先生と同じ時期に、ニューヨーク大学(NYU)のセベロ・オチョア先生(ノーベル賞受賞者)の研究室でポスドクをしていたのです。
―― ワイスマン研では、谷口維紹(たにぐちただつぐ)先生(東京大学生産技術研究所 炎症・免疫制御学社会連携研究部門)とご一緒されているのですね。
長田氏: 1年間のオーバーラップで、谷口先生の最後の1年と私の最初の1年が一緒でした。IFN(インターフェロン)を担当していた谷口先生が癌研に戻り、私はその後を引き継いでIFNをやり始めました。癌研で谷口先生がIFNβ、ワイスマン研で私がIFNαのクローニングに取り組むことになりました。当時、私たち以外にも、アメリカやヨーロッパのたくさんの研究室で同じことが試みられ、ものすごい競争になっていました。
―― その戦国時代を勝ち抜かれた……。
長田氏: すごい競争でしたが、それを気にしていても始まらない。クローニングにほぼ1年かかりましたが、幸いなことに成功しました。そして、成功した時の反響は想像を絶していました。
当初、IFNクローニングの論文は、PNAS(Proceedings of the National Academy Sciences of the United States of America;米国科学アカデミー紀要)に投稿するつもりで準備していました。ところが、投稿直前になってワイスマン先生、「PNAS ではなくNature に投稿しよう」と言い出されました。急いで原稿を書き直し、先生自らロンドンのNature 編集部に持って行かれました。郵送ではなく、自分で持って行かれた。意気込みが違ったのですね。
―― それは長田先生の世界デビュー論文でもあったわけですね。
長田氏: 1980年3月の私を筆頭著者としたNature の Article。チューリッヒへ渡航して2年半、初めての論文です。そして6月には谷口先生と共著でIFNαとβが似ているという論文、10月にはIFNの染色体遺伝子の構造を記載した論文が、いずれもNature の Article として載りました。結局、4年間のチューリッヒ留学中にNature の論文4報を含め12本の論文を書きました。
―― Nature の存在は大きいと思われましたか。
長田氏: 最初の論文を出した時の反響はとても大きく、リプリントの請求が山ほど来ました。普通に対応できる量ではありません。IFNががんの薬になるかもしれないという期待があったことから、患者さんからの反応もすごかった。世界中から、IFNを分けてほしいという手紙が来たのです。ワイスマン先生は、すべての人に「今はそんな状況ではない。薬として使えるようになるには数年かかるであろう」と返事を書かれました。1000通は超えていたと思います。
サイエンスが社会にいかに大きなインパクトを与えるか。それにいかに対応すべきか。教えられました。
―― 1982年に日本に戻られました。
長田氏: 東大医科研に助手として帰国しました。強い動機があったわけではありません。今の独立准教授のような制度はなく、給料も安かったけれど、自分の好きなことはできました。日本に帰ってサイエンスができる。それでとても幸せでした。
アポトーシスの解明へ
―― 先生の大きな業績に、アポトーシス(プログラム細胞死)のお仕事があります。
長田氏: きっかけは私が医科研に所属していた頃、東京都臨床医学総合研究所の米原伸(よねはらしん)先生(現、京都大学大学院生命科学研究科 高次遺伝情報学分野)と共同研究したことに始まります。彼とIFNのシグナル伝達をやりたいと考えていました。米原先生は、INF受容体に対するモノクローナル抗体を樹立しようと研究を始めました。この抗体の存在下でウイルスを感染させると、INFは作用できず細胞はウイルスにより死ぬはずです。ところが彼が単離した1つの抗体、それを作用させるだけで、細胞が死んでしまったのです。米原先生はこれを抗Fas抗体と命名しました。
「これはいったい何なのだ!」というところから研究が始まったのです。わからないことだらけです。
まずこの抗体が認識するタンパク質(Fas)の遺伝子を単離しました。遺伝子配列から類推されるFasはサイトカイン(免疫細胞の情報伝達物質)に結合する受容体に似た構造を持ち、これを発現する細胞に抗Fas抗体を作用させるとアポトーシスを起こして死にました。このことからFasはアポトーシスのシグナルを伝える受容体ではないかと考えました。最初の論文は1991年にCell に発表しました。
Fasが何らかの遺伝病に絡んでいないかと思い、米国国立衛生研究所のジェンキンズ博士にお願いしてマウスFas遺伝子の染色体の位置を調べました。すると、この遺伝子はマウス19番染色体上のlpr変異をおこす遺伝子とほぼ同じ領域にありました。lpr変異マウスではリンパ節や脾臓が腫れあがります。そこで、「アポトーシスを起こすFasが機能しないために細胞が死ななくなり、その結果、リンパ節や脾臓が大きくなるのでは」と思って、lpr変異マウスにおけるFas 遺伝子の構造を調べました。すると、まさにそのとおり、lpr変異マウスではFas遺伝子に突然変異がおこり、機能しなくなっていました。この論文は92年のNature のArticleになりました。
—— Fasというのは何なのですか。
長田氏: アポトーシスのシグナルを細胞に伝達する受容体です。例えば、インスリンはその受容体と結合することで糖の取り込みやグリコーゲンの合成を促進します。また、増殖因子は、その受容体と結合することで、細胞を増殖させます。Fasの場合は、アポトーシス、すなわち細胞を殺すためのシグナルを細胞に伝えます。
「サイトカインの受容体のような構造をもつFasが細胞膜上に存在している。細胞を殺すための受容体があるのであれば、それに結合する殺すための因子があるはずだ」と推論しました。確かに、Fasに対するリガンド(受容体に結合する分子)が見つかりました。論文は93年のCell に出しました。
—— 細胞を殺すアポトーシス因子が、Fasリガンド。
長田氏: そう、これがデスファクター(死の因子)としてFasに結合するのです。
—— 細胞の中で何が起こっていくのですか。
長田氏: アポトーシスが起こると、カスパーゼというタンパク質分解酵素が活性化されます。カスパーゼは私たちがICADと命名したDNA分解酵素のインヒビター(阻害因子)を切断・不活化し、その結果、自由になったDNA分解酵素が染色体DNAを分解します。この仕組みがわかったのが1997年です。
実験結果を2報の論文に分けてNature に投稿しました。査読者の好意的なコメントとともに「10日間で修正できるようであれば、1998年1月1日号に掲載する」というエディターからの手紙が来ました。インターネットは存在しない時代です。懸命に書き直して、大阪中央郵便局に持って行きました。晴れてNature の1月1日号に、Article と Letter として掲載されました。
これらは、1998年に世界で発表された論文の中で、最も多く引用されました。
時間をかけて、よい仕事を
—— 免疫学は病気と密接な関係がありますね。
長田氏: はい、最近、PD-1と呼ばれるT細胞(リンパ球の一つ)の受容体に対する抗体がメラノーマ(皮膚がんの一種、悪性黒色腫)や肺がん患者にとてもよい治療効果を示しています。強調したいのは、そこまで来るにはとても長い時間がかかっているということです。
PD-1は1992年、「プログラム細胞死」に関与している分子として同定された分子です。その分子が、本庶佑(ほんじょたすく)先生(京都大学大学院医学研究科 連携大学院講座)をはじめとする多数の研究者の20年に及ぶ努力によって、がんの薬となりました。生命の成り立ちを明らかにする基礎研究はとても重要です。そのような研究こそ、社会に役に立つのだと思います。しかし、5年やそこらでは、決して薬にはなりません。
科学の世界は、考えたこと、予想したことと違うことが出てくるからおもしろい。どこにどう跳ぶかわからないからおもしろいのです。
—— 貴重なお話、ありがとうございました。
聞き手は松尾義之(科学ジャーナリスト)。
Author Profile
長田 重一
大阪大学免疫学フロンティア研究センター教授。ロベルト・コッホ賞(1995)、日本学士院賞・恩賜賞(2000)などを受賞。文化功労者(2001)、日本学士院会員(2011年)、米国科学アカデミー外国人会員(2015年)。