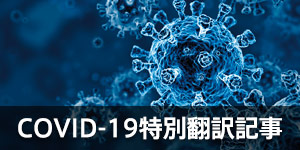日本の地震学、改革の時
原文:Nature 472, 407–409 (号)|doi:10.1038/nature10105|Shake-up time for Japanese seismology
東京大学のロバート・ゲラー教授は「日本政府は、欠陥手法を用いた確率論的地震動予測も、仮想にすぎない東海地震に基づく不毛な短期的地震予知も、即刻やめるべきだ」と主張する。

石橋克彦・神戸大学名誉教授をはじめとする一部の地震学者が、20年以上も前から地震や津波による原子力発電所の損壊と放射性物質の漏洩の危険性を指摘してきたにもかかわらず、この指摘はほとんど顧みられることはなかった。3月11日のマグニチュード9.1の東北地震(東日本大震災)のあとでさえ、テレビなどで今回起きた地震と津波を「想定外」と語る解説者は多い。
ならば、「想定内」の地震とは何なのか。それは、日本政府の地震調査研究推進本部(以下、推進本部)が仮定した、地域ごとの固有地震を指していると思われる。そこでは、それぞれの地域に対して、断層パラメータなどを入力データとして、確率論的地震動予測地図1を導き出している(地図を参照)。

毎年日本政府は、確率論的地震動予測地図を公表している。しかしながら、1979年以降、10人以上の死者をもたらした地震はリスクが低いとされた地域に起きている。 | 拡大する
Source: 地震調査研究推進本部
全国地震動予測地図
-地図を見て 私の街の 揺れを知る-
地図編 2010年版
確率論的な地震動予測地図といえば信頼性が高いようにみえるかもしれないが、予測に用いられた手法が検証されるまでは、単なるモデルにすぎない。この地図で最も危険だと評価されているのが、東海、東南海、南海という3つの地域の「シナリオ地震」である。しかし現実には、1979年以降、10人以上の死者を出した地震は、この確率論的地震動予測地図において、比較的リスクが低いとされてきた場所で発生している。この矛盾からだけでも、確率論的地震動予測地図およびその作成に用いられた方法論に欠陥があること、したがって破棄すべきであることが強く示唆される。またこれは、昨今の一連の固有地震モデル(およびその類型である地震空白モデル)に対しても否定的な結果2-4を示しており、確率論的地震動予測地図を作る際に仮定した物理モデルが、本来の地震発生の物理的過程と根本的に異なる誤ったものであることを示唆している。
過去100年間で、沈み込み帯におけるマグニチュード9以上の地震は5回発生している(1952年カムチャッカ、1960年チリ、1964年アラスカ、2004年スマトラ沖、2011年東北)。この事実は、沈み込み帯の地震の最大規模は、その地質学的条件にあまり依存しないことを示唆している5。これまでも大津波は東北地方の太平洋沿岸を頻繁に襲ってきた。1896年の明治三陸津波は最大38mにも達し、2万2000人以上の死者を出した。また869年の貞観津波の高さは、記録によると、今回の3月11日に発生した津波にほぼ匹敵するものとされている。
もし、世界の地震活動度と東北地方の歴史記録が、地震の危険性を見積もるときに考慮されていれば、もちろん時間・震源・マグニチュードを特定するのは無理としても、3月11日の東北地震は一般には容易に「想定」できたはずである。とりわけ、1896年に起きた明治三陸津波はよく認知されており、かつ記録もなされているので、こうした地震への対策は、福島原子力発電所の設計段階で検討することは可能であったし、当然そうすべきであった。
東海地震
1960年代、プレートテクトニクスは固体地球科学の基本的な枠組みとして一般的に認められるようになった。多くの国において、大地震の長期予測を行うために、地震活動度とプレートテクトニクスを結びつける研究が進められた。その考えはきわめて単純だった。しばらくの間大きな地震が発生していない「地震空白域」では大地震の発生が差し迫っている、という仮定である。しかし、この地震空白域仮説は実証されなかった2。何万年もしくはそれ以上の時間スケールにおいて、地震や非地震の総すべり量とプレート間の相対運動の量は一致しなければならない。しかし、現在では、このプロセスは、定期的でも周期的でもないことが判明しており、3月11日の地震はこれを確認させるものであった。
しかしながら、地震空白域仮説は1970年代半ば、世界の地球科学コミュニティで流行した。このとき、東海沖のプレート境界こそが、マグニチュード8が起こると考えられる地震空白域である、と何人かの日本の研究者が主張した6。隣接する東南海および南海地域もまた、地震空白域とされた7。これらの地域では1975年以降大地震は発生していないにもかかわらず、いまだに日本政府は全国で最も危険な領域としている。
過去30年以上の間、政府の報道官および推進本部(またその設立前の関連組織)に所属する研究者は、「東海地震」という単語を頻繁に使ってきた。そのため、国民やマスメディアは、東海地震を単なる任意のシナリオではなく、「本当の地震」と思うようになった(日本語グーグルの検索では178万件ヒットする)。その結果、時計が時を刻むように、あらかじめ決まっているマグニチュード8の地震が、近い将来東海地域を確実に襲うと国民に思い込ませてしまった。「東海地震」および「東南海地震」と「南海地震」という言葉は、現実として起こっていない以上、使用すべきでない。
予測が不能な地震
地震学の歴史を通じて、数時間もしくは数日間前に地震の予知を行うということは、極めて懐疑的にみられてきた8(http://go.nature.com/ahc6nxも参照)。しかし、1960年代後半から1970年代初めに、はじめはソ連の研究者によって、続いて米国の主要機関の研究者による肯定的な研究が登場し、楽観ムードに変わっていった。Nature の1973年の社説には、「状況は核分裂が突然現実のものとなった1939年にいくつかの点で似ている」と記載されている9。また、ほぼ同時期に、Science といくつかの主要な専門誌上にも肯定的な報告が掲載された。
これらの肯定的な報告は、地震の前兆を観測したという主張に基づいたものであった。1973年のNature の社説が取り上げた研究では、地殻の地震波速度が10〜20%減少した後に正常値に回復するときは、地震が差し迫っている信号である、と報告している。しかしながら、24万人が死亡したとされる1976年の中国の唐山地震は予知(が)できなかった。そして、1970年代後半になると、大半の研究者は、このような地震の前兆報告が誤りであったことを認識するようになった。地震予知のバブルはこうしてはじけたが、多くの似たような例(ポリウォーター、常温核融合など)と同様、いくつかの国において、今でもわずかに残った一部研究者が地震の前兆という主張を続けている。
根拠のない予知法
1970年代半ばに差し迫っているとされた東海地震に関する議論は、日本中をなかばパニック状態にした。この状況を利用して、気象庁や大学の科学者は1978年に「大規模地震対策特別措置法」(以下、大震法)の制定を促した。大震法によって定めた制度により、気象庁は常時観測(写真を参照)を運用して「東海地震」が発生する前兆を検出しようとしている。前兆と思われる信号が観測された場合、5人の地球物理学者から構成される「地震防災対策強化地域判定会」がデータを精査し、気象庁長官が内閣総理大臣に報告、閣議を経て広い地域においてほぼすべての活動を停止する警戒宣言を発令する、という仕組みになっている。

Source: 気象庁
他の国で前例がない大震法は、信頼性の高い地震の前兆が存在することを前提としている。1944年に日本で起きた東南海地震に対する測地学的前兆現象に関する一報告(文献6の図2を参照)に基づき、測地学的な滑りが気象庁の観測の主な対象となっている。震央地域から遠い場所で観測された1944年のデータは、本震の直前に断層の深い部分がゆっくりとした滑りによって数cm隆起したものと解釈された。残念ながらこのデータは、今では時代遅れの測量技術を使用して測定されたもので、かなりの不確実性を伴う。現に、この種の前兆現象は、GPSや他の近代的な測定技術では見つかっていない。1970年代に米国で観測された測地学的な前兆(パームデールバルジと呼ばれた)が報告されたが、結局は誤りであると判明した(参照文献8のセクション3.4を参照)。
研究者は国民と政府に「想定外に備える」ことを勧告しなければならない。
このように極めて疑わしい1944年の例を根拠として大型観測研究計画を進めるのは、適切であるとは言い難い。さらに、日本政府がいまだに法的に拘束力のある地震予知体制を運用していることには、驚きを禁じえない。気象庁のホームページには、「体制が整っていて予知のできる可能性があるのは、現在のところ(場所)駿河湾付近からその沖合いを震源とする、(大きさ)マグニチュード8クラスのいわゆる『東海地震』だけです。それ以外の地震については直前に予知できるほど現在の科学技術が進んでいません」という記述がある。しかし、1978年当時と比べて現在では観測点の数ははるかに増えている。もし本当に「東海地震」の予知が1978年当時にも可能であったならば、現時点ではすべてのマグニチュード8の地震が予知されているはずである。
正直な議論の必要性
東海地震予知体制が30年以上にわたって継続されているにもかかわらず、多くの主流の日本の地震学者は何の異議も申し立てていない。その理由は多少複雑である。第1に、多くの研究者がさまざまな点(予算配分、委員ポストなど)で癒着している。第2に、政府決定には名目上の審議があるが、審議会は官僚が指名する委員から構成されている。第3に、説得力のある批判は紙媒体の報道機関で取り上げられることがあるが、放送マスコミではほとんど無視されるために、インパクトが乏しい。第4に、政府は「記者クラブ」制度を介して、直接マスコミにその見解を伝えることができる。そして、しばしば報道記者は科学の知識に乏しい。最後に、大震法が有効である限り、政府は、東海地震予知には法的な拘束力があると主張することができる。
今こそ、地震予知が不可能であることを率直に国民に伝え、東海地震予知体制を廃止して、大震法を撤廃する時である。日本全土が地震の危険にさらされているのであって、現在の地震学では、特定の地域のリスクレベルを的確に評価することはできない。その代わりに、研究者は国民と政府に「想定外に備える」ことを10勧告しなければならない。そして、研究者は知っていることと知らないことの両方を正確に客観的に知らせなければならない。地震学の将来の基礎研究は、物理学に根ざし、厳密に精査され、顔の見えない官僚によってではなく、日本の一流の科学者によって導かれなければならない。
(翻訳:本人)
著者は東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授。
参考文献
- Headquarters for Earthquake Research Promotion, National Seismic Hazard Maps for Japan, 2005, http://go.nature.com/yw5e92.
- Kagan, Y.Y. & Jackson, D.D., J. Geophys. Res., 96, 21419-21431 (1991).
- Kagan, Y.Y., Bull. Seism. Soc. Am., 86, 274-285 (1996).
- Newman, A., Schneider, J., Stein, S. & Mendez, A., Seismol. Res. Lett., 72, 647-663 (2001).
- McCaffrey, R., Geology, 36, 263-266 (2008).
- Ando, M., Tectonophysics, 25, 69-85 (1975).
- Ando, M., Tectonophysics, 27, 119-140 (1975).
- Geller, R.J., Geophys. J. Int., 131, 425-450 (1997).
- Nature, 245, 174 (1973).
- Kanamori, H., Seismol. Res. Lett., 66 (1), 7-8 (1995).
Supplementary Information
- 気象庁:地震予知について