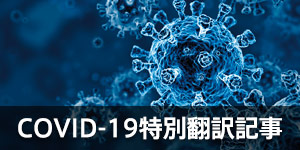リスクの高い研究に関する論文の掲載
原文:Nature 485, 5(号)|doi:10.1038/485005a|Publishing risky research
バイオセーフティーに関する国際基準に不備があり、バイオセキュリティー上の懸念から研究者のモチベーションがそがれている。現在のインフルエンザ研究には、こうした重大なリスクがある。
今週、ウィスコンシン大学マディソン校(米国)の河岡義裕をリーダーとする日米の共同研究チームの論文 “Experimental adaptation of an influenza H5 HA confers respiratory droplet transmission to a reassortant H5 HA/H1N1 virus in ferrets (インフルエンザH5赤血球凝集素の実験的適応がもたらすフェレット間でのH5 HA/H1N1再集合体ウイルスの飛沫感染)”(M. Imai et al. Nature (2012)) が Nature オンライン版に掲載される(2012年5月3日号7、13頁とH.-L. Yen and J. S. M. Peiris Nature 10.1038/nature11192; 2012も参照)。去る2011年8月、人為的遺伝子操作によって鳥インフルエンザが哺乳類間で伝播するようになったことを報告する2編の論文が投稿され、わずかな数の変異でその伝播が生じることに科学的関心が集まると考えられた。河岡の研究チームの論文とエラスムス医療センター(オランダ・ロッテルダム)の Ron Fouchier が主導する研究チームの論文である。後者は、まもなく Science に掲載される予定だ。
Nature で盛んに論じられてきたように、それぞれの論文については、各出版社での審査が実施されている間に、米国バイオセキュリティー科学諮問委員会(NSABB)は独立して論文の評価を行った。そして2011年11月、NSABBは重要な方法とデータの論文公表を差し控えることを勧告し、それが両誌に伝えられた。この勧告に法的拘束力はないが、研究者や出版社を萎縮させる効果があった。それから数か月間、国民的論議が繰り広げられ、さらには、インフルエンザの専門家とその他の利害関係者が参加する2日間の会議が二度も行われた。最初の会議は世界保健機関(WHO)によって開催され、2回目の会議は、3月下旬にNSABBによって開催された。この会議の後、NSABBは、基本的に、当初の姿勢を翻し、そして Nature は、論文公表に踏み切ることを独自に決定した。
得られた教訓
経済学者のジョン・メイナード・ケインズは、「事実が変われば、私は考えを変える」と言ったと伝えられている。しかし、NSABBの1回目と2回目の審議で、河岡論文の重要な科学的要素に変化はなかった。今考えれば、そして、特に論文公表に反対する勧告がインフルエンザ研究に計り知れない影響を与えることを考慮すれば、NSABBの当初の審議が不十分であったことは明白だ。それでもNSABBは、生物学的研究のセキュリティー上のリスクを予測し、精査することをめざす機関として世界的にもユニークな存在であり、そのような議論の場を保持することが望ましい。もし今回問題となったのが架空の事例であれば、NSABBの最初の勧告で、これほど貴重な、あるいは機敏な論議は巻き起こらなかっただろう。しかし、研究コミュニティーでは、NSABBのプロセスに関する懸念が語られている。そうした懸念は正当なものであり、NSABBのプロセスは見直しが行われるべきだ。
大学の研究室に秘密情報を提供した場合に、その秘密が長期間にわたって守られる とも思えない。
今後の行動や方針を示唆する教訓がいくつかある。第1に、今回問題となった論文を単に不受理とするのではなく、論文の重要知見を省略した編集版を掲載する可能性についての検討が長期間にわたって行われたが、それは価値あるものだったと言える(もし Nature がセキュリティーの専門家から論文公表のリスクが利益を上回っていると助言されていれば、不受理という選択肢は長い間残っていたと考えられる。)。このほかに、第三者機関が論文の完全版を特定の読者だけに頒布するという選択肢もあった。これらの選択肢を詳細に検討したうえで、我々 Nature の編集者たちは、Nature に掲載される論文に関して、当分の間、編集版の掲載、限定頒布という2つの選択肢を考えないことを決定した。重要な結果や方法の省略された論文では、その後の研究を進めることも、査読を行うこともできない。さらに、我々は社内外でかなり検討を重ねたものの、論文の閲覧を許される者と許されない者を適切に判定するための機構や基準を考えつかなかった。それに、大学の研究室に秘密情報を提供した場合に、その秘密が長期間にわたって守られるとも思えなかった。
研究結果が公共の利益に資すると同時にセキュリティーに対する脅威にもなる分野では、制限付きの論文発表という選択肢がないこと自体がリスクであることを我々は承知しており、このジレンマから脱する方法を積極的に模索したいと考えている。
第2に、こうした議論がなされることで生じる一つの大きなリスク、つまり若手の研究者がセキュリティー上の制約を受ける分野への参入を思いとどまる可能性だ。しかし、バイオセキュリティーの専門家の考え方は、一般に認識されている以上に楽観的である。Nature の知る限り、安全保障機関による数々の公式評価においては、河岡論文の公開勧告が導き出された。その1つが、Nature が米国外の生物防衛機関に委嘱した独立評価で、助言内容は go.nature.com/wglsea に掲載されている。また、その後行われたバイオセキュリティー研究者との議論では、「公衆衛生や科学にとっての利益があれば、論文公開すべきだ」という点で、特筆すべき意見の一致があった。この秘密主義の分野に属する科学者が、トラブル発生の可能性がある時に最も頼りになるのはオープンな科学的活動を行うことだと考えていることがわかったのは有意義だった。
3番目に最も重要な教訓はバイオセーフティーに関するものである。ここには現実的な懸念がある。つまり、ヒトはH5赤血球凝集素タンパク質を有するインフルエンザウイルスに対する免疫がないため、哺乳類に感染できるH5ウイルスが偶発的に流出した場合にヒトからヒトへと伝播すれば、パンデミックとなる可能性があるのだ。NSABBの第2回審議において、河岡の明快なプレゼンテーションは重要な要素の1つであった。河岡は、自らの研究チームの非常に厳格なセキュリティープロセスとセキュリティー体制(物理的配置、研修、研究チームのメンバーが払っている相当程度の注意を含む)を示した。
このように安心感の得られる状況は、世界中に存在しているわけではない。河岡の研究室は(河岡論文で十分に説明されているように)、“BSL-3 enhanced(バイオセーフティーレベル3レベルの実験室でバイオセーフティーレベル4レベルに相当する安全措置を実施する)”という基準を満たしている。WHOの会議では、この基準が必須とされ、これよりも明らかに厳しいBSL-4基準が義務づけられると、閉鎖に追い込まれる研究室が出るという懸念が表明された。ただ、“BSL-3 enhanced”は正式に定められた基準ではない。さらに、十分な規制制度、そして研究室での頑強な安全風土がすべての国々に存在しているとは限らない。このことは、インフルエンザの伝播能力について研究している人たちが、その研究の自主的な一時停止を続けている中で重要な論点となっている。
WHOは、まもなくバイオセーフティーの国際基準に関するガイドラインを公表することになっている。このガイドラインでは、「良好なガバナンス」の重要論点と重要側面が明確に示されるが、その実施を強化するための枠組みを提示するまでには至らないと予想されている。そのような枠組みこそが、危険な生物を取り扱う研究者やその研究に資金を提供し、その論文発表に関係する者にとっての緊急の懸案事項なのだ。