
sinology / Getty Images
壊れゆく生物圏における将来の食物
健康的で持続可能な食物を世界に供給しようとすることは、今も昔も極めて難しい課題である。先日開催されたNature Café「Environmental Stress and Food Crisis(環境ストレスと食糧危機)」では、専門家たちが集まり、この重要な目標を達成するために検討されている方法について議論が行われた。
Produced by


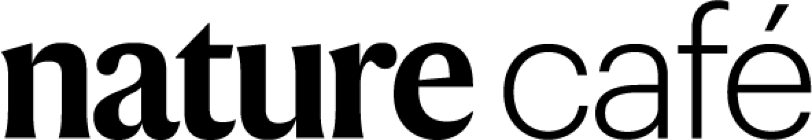
国連の発表データによれば、世界では約6億9000万人が飢餓状態にあるという。国連は、「持続可能な開発目標(SDGs)」の1つとして、2030年までに「飢餓をゼロに」という目標を掲げているが、このままでは、飢餓に苦しむ人の数は2030年までに8億4000万人を超えてしまう。さらに、現在、世界の食料システムの復元力は、COVID-19パンデミック(世界的流行)、東部アフリカの蝗害(バッタ類の大量発生により起こる災害)、悪化する生物圏(陸上、水中、空中)など、さまざまな危機からさらなる圧力にさらされている。
岡山大学副学長で、ユネスコ(国連教育科学文化機関)の「持続可能な開発のための研究教育」のチェアホルダーを務める横井篤文は、「『なぜ』行動を起こすのかではなく、『どのような』行動を起こすのかを考えるべき時です」と話す。「地球を守りながら、現在の人口のニーズを満たさねばならないのです」。
株式会社 林原が協賛し、2020年11月13日にオンライン形式で開催された、Nature Café「Environmental Stress and Food Crisis」では、「世界の需要を満たすのに十分な食料をどうやって生産するか」という複雑な問題が議論された。
健康の課題
人類と地球の健康には、重要な課題が3つある。1)ますます増加する人口への食料供給、2)環境への影響の低減、3)変わりゆく気候への適応だ。
環境世界の食料システムは、現時点で80億人分の食料、飼料、生体材料を生産する必要があり、2050年の人口は、100億人に達していると予想されている。
環境チューリヒ工科大学(スイス)の持続可能な食品加工グループで教授を務めるAlexander Mathysは、「世界の食料システムは、国連の17のSDGsのゴールのうち、少なくとも12のゴールに関係しています」と話す。
Mathysは、「現在の食料生産は、環境に極めて大きな影響を及ぼしています」と続ける。
農業は、世界で最大の微粒子発生源の1つである上、生物多様性の損失と気候変動を引き起こしている。さらに気候変動は、世界のさまざまな場所で、どの作物が栽培可能であるかに影響する。
コロラド州立大学土壌作物科学科(米国)のNathan Muellerは、「食料格差に対処するには、需要を減らし、土地利用を拡大させることなく生産量を増やす必要があります」と話す。
地理空間科学は、リモートセンシング、国勢調査などの調査データ、現場でのモニタリング、グリッド化や調整を行ったデータセットなど、さまざまな情報源のデータを使い、このような課題を研究者が理解して取り組むのに役立つ興味深い新たなツールをもたらしている。
地理空間データ解析は、世界の作物収量を追跡し、潜在的な収量と実際の収量にギャップがある場所を見いだすとともに、栄養素の過不足、肥料の使用量、温室効果ガス生成量、あるいは農地が自然の植生に取って代わっている場所など、環境的に重要な変数をマッピングすることができる。さらに、気候が変動した際に、地理空間データは作物をより適した気候の場所へ移す手引きにもなっている。
ワンヘルス
ワンヘルス(One Health)イニシアチブは、人々、動物、地球の健康状態の最適化を実現するために、地域、国家、世界のレベルで活動することを目指している。「農業は、人々、動物、地球の健康を保護し、促進する役目を果たさなければなりません」。こう話すのは、ジェロナ・グラ大学ライプニッツ農業工学・バイオエコノミー研究所(ドイツ)のBarbara Amonだ。「健康と農業の連鎖の起点に投資する必要があります」。
最適化は、輪作、窒素固定においてマメ科作物を使用すること、栄養素の流れが都市部への一方通行にならないよう徹底することなど、栄養素を管理したりリサイクルしたりすることによって行うことができる。家畜の健康福祉を改善し、より持続可能な製品を使うことによって、家畜動物を原料とする食料の環境への負荷は軽減されるだろう。消費者も、食料やバイオマテリアル、エネルギーを有効に使うことで重要な役目を果たす。
家畜の健康福祉、そして家畜と環境の相互作用を可視化することは、こうした介入の効果や経済性を理解する上で不可欠だ。低所得国であろうと高所得国であろうと、農家はいつも、このような介入施策にかかる費用を懸念している。農場において結果を測るためには費用も労力もかかるため、データは、研究室での実験や、モデル化、シミュレーションによって得るのが一般的だ。

JamesBrey/E+/Getty Images
新たな食料源
人間が健康を保つためには、1日に体重1kg当たり0.8gのタンパク質が必要である。肉類は重要なタンパク源だが、その大規模な生産によって環境への負荷が増大している。研究者たちは、直接的には食品の材料として、間接的には飼料として、新たなタンパク源を探求している。
豆類は優れたタンパク源であり、直接食べることもできれば、パンやパスタなどの食品に混ぜたり、動物に与えたりすることもできる。昆虫は一部の地域では食料とされており、中期的には「昆虫工場」での食物や飼料の生産が増加すると予想されている。また、藻類などの単細胞生物を都市部や農村部のバイオリファイナリー(生物精製所)で培養してさまざまなタンパク質を生産し、残留バイオマスを肥料や飼料として使うという長期的な取り組みもある。実験室で培養した筋肉組織を食肉として使うアプローチについては市場化までの道のりはまだ遠い。こうした代替品が利用可能になるかどうかは、技術の完成度と経済的規模による。
「藻類や昆虫などの新しいタンパク源は、期待されたほど活用されておらず、まだまだ最適化されていないのです」とMathysは言う。「消費者が食料源として受け入れてくれるかどうかを、消費者と共に確認する必要もあります」。
農業への介入の測定
コーネル大学(米国)、国際食料政策研究所(米国)、国際持続可能な開発研究所(カナダ)の共同事業であるCeres2030は、論文約50万編に記載されている介入を、応用機械学習と分析論を用いて評価した。
コーネル大学国際開発学科研究データエンゲージメントのJaron Porcielloは、「エビデンスの基盤に大きな問題がありました」と話す。「介入が単独で成功することはほとんどなく、介入を農家と共同で評価した論文もほとんどなかったことが分かったのです」。
世界の飢餓に影響を与えて食糧危機による環境への影響を軽減するためには、社会政治的な文脈に基づいた全体論的な手法で変革を図ることが不可欠だ。事態はこの上なく切迫している。横井が言うように、「私たちに別の惑星はありません」。
グリーン・バイオマテリアル
Nature Caféの直後に、協賛の株式会社 林原とネイチャー・リサーチ・カスタムメディアで、「環境と食料の持続可能性に向けたグリーン・バイオマテリアルに基づくアプローチ」をテーマに議論が行われた。同社社長の安場直樹は今回のイベントについて、「持続可能な環境、食料、食料システムの問題を解決する上で、天然由来のバイオマテリアルの応用とその可能性に関する知識を共有する絶好の機会となりました」と話す。招待された参加者と同社の上席研究員たちは、生物を基盤とする理想的な材料の特徴や、そうした製品をさらに広く普及させる際の障害に関して議論を行った。
幅広い議論の中で、参加者から、自然には廃棄物という概念がないという指摘があった。つまり、既存の廃棄生成物を原料として利用するバイオマテリアルは、本質的に持続可能ということである。
参加者たちは、国連の持続可能な開発目標の「飢餓をゼロに」に向けて私たちの社会を着実に前進させる上で、学術界と産業界と政策立案者の連携がカギであるということで合意した。
林原のような企業は、創造性やスタートアップ企業を、材料や物資を支援して育むことによって、優れたアイデアを研究室の外へと引き出す役割を果たすことができる。時には、政府が新たな規制によってイノベーションを推進することができ、新製品の認証によって、より広範な採用につながることもある。
参加者の1人は、米国でのBTトウモロコシの事例を挙げた。新たな遺伝子改変食品として、その導入には懸念があったが、科学者、政府、産業界で構成されるワーキンググループが発足することで、懸念への対処が容易になったという。
原文:Food for the future in a degrading biosphere
Advertiser retains sole responsibility for the content of this article
招待参加者

横井 篤文
岡山大学副学長(特命(海外戦略)担当)
ユネスコ(国連教育科学文化機関)
「持続可能な開発のための研究教育」チェアホルダー

Nathan Mueller
コロラド州立大学
土壌作物科学科/生態系科学・持続可能性学科助教

Barbara Amon
ジェロナ・グラ大学
ライプニッツ農業工学・バイオエコノミー研究所准教授

Alexander Mathys
チューリヒ工科大学
持続可能な食品加工教授

Jaron Porciello
コーネル大学
国際開発学科研究データエンゲージメント副理事

Anne Mullen
Chief Editor, Nature Food

