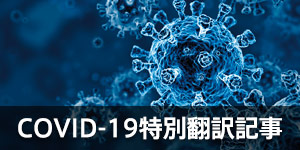福島:放射能の恐怖の影響
原文:Nature 493, 290-293 (号)|doi:10.1038/493290a|Fukushima: Fallout of fear
福島の原発事故後、住民は放射能による身体的な影響からは守られているものの、精神面への影響は深刻だ。
被災地からの声
図内をクリックすると、原発事故から影響を受けた人々の声を聞くことができます。
25 km
30 km
人々
地域
福島市
川俣町
飯舘村
浪江町
福島第一原子力発電所
楢葉町
放射能のレベル(毎時マイクロシーベルト)
> 19.0
9.5 – 19.0
3.8 – 9.5
0.5 – 3.8
< 0.2
佐藤幸子さん

川俣町出身の佐藤さんは、科学者や政府により川俣町の安全性が保証されているにも関わらず 、90キロ北部に位置した山形市に避難している。当局への不信感を抱く佐藤さんは、 当局関係者は人々の福利よりも自分たちのことにしか興味がないと考えている。
Photo credit: Geoff Brumfiel
佐藤幸子さん
戸川家

戸川家は、一家5人で川俣町はずれの仮設住宅に住んでいる。両親は家族の将来を懸念している。由香さん(中央)は、仮設住宅での生活により不安感が募るいっぽうであると述べている。
Photo credit: Geoff Brumfiel
戸川由香さん
大久保健二さん

ストレスにより、大久保さんは大量のアルコールを摂取するようになった。仮設住宅から故郷である飯舘村に近い川俣町へ移った。飯舘村に数週間戻っては、人気の無い通りでゴルフの練習をする。
Photo credit: Geoff Brumfiel
大久保健二さん
伊藤巨子さん

事故後、伊藤さんは年老いた母親の介護をするため夫と共に楢葉町に残った。3人が住む町には水道水も無ければ、隣人も居ないが、3人は幸せに暮らしており引っ越す予定は無い。
Photo credit: Geoff Brumfiel
伊藤巨子さん
山本博美さん

山本さんは浪江町で英語教師をしていた。東京郊外へ避難したが、退屈になりうつを訴えるようになった。現在は福島県に戻り、新しい学校を開校させた。
Photo credit: Geoff Brumfiel
山本博美さん
福島市

福島県の県庁所在地。福島市は、原発事故に対処するうえでの拠点地となってきた。
Photo credit: Geoff Brumfiel
川俣町

川俣町のはずれにある仮設住宅には、戸川一家を含む原発事故避難者が暮らしている。
Photo credit: Geoff Brumfiel
飯舘村

飯舘村の放射能レベルは高いため長期にわたって住居が制限されているが、短期間の帰宅は許可されている。多くの住民が日中戻ってきては、垣根を整えたり避難所に連れていけないペットたちに餌をやったりしている。
Photo credit: Geoff Brumfiel
浪江町

浪江町は、海沿いの小さな町だ。原発後、避難勧告が真っ先に発令された地域の一つである。浪江町の住民の多くは、福島県の他の地域にある仮設住宅で生活している。
Photo credit: Noriko Hayashi/Panos
福島第一原子力発電所

2011年3月、福島第一原子力発電所を襲った津波によりメルトダウンが発生した。12万人以上の住民が避難を余儀なくされ、15万人がいまだ避難生活を送っている。
Photo credit: TEPCO
楢葉町

海岸沿いを襲った津波による被害の撤去作業は最終段階にある一方で、楢葉町では放射能のため復旧作業が難しく、津波による傷跡がいまだ顕著に残っている。
Photo credit: Geoff Brumfiel
戸川謙一さんが帰宅して真っ先にすることは、ビデオゲームの電源を入れることだ。3人の子供を抱える一家の柱である戸川さん39歳は、焼酎を飲みながらビデオゲームに毎晩何時間も費やす。テレビの前で寝入ってしまうことも多々あり、夜中に寒さで目が覚めては妻が眠るベッドへもぐりこむ。
過去25年間で最悪の原発事故後、戸川さん一家は2年近くにわたり避難生活を続けている。2011年3月11日、巨大地震が東北地方の太平洋沖を襲った。福島第一原子力発電所に13メートルの高さの津波が押し寄せたことを引き金に、6機ある原子炉のうち3機でメルトダウンが発生した。その翌日、1号機が爆発する数時間前に、戸川さん一家は発電所から10キロ離れた自宅を後にした。避難区域から逃れ、現在は福島県北東に多数立ち並ぶグレーの仮設住宅の一角に住んでいる。わずか30平方メートル、3部屋の空間に一家5人は身を寄せている。冬の冷え込みは厳しいが、窓の隙間風対策はお粗末なものである。
この1年半にわたり、一家の精神的な健康は危機にさらされてきた。原子力発電所の作業員だった謙一さんは、柔道家で以前は友人たちとよく出かけていたものだが、原発事故の後柔道サークルのメンバーはばらばらになった。最近の謙一さんは運動量が減り、友人と出かけることもほとんどない。お酒の量が増え、体重が増加した。
妻の由香さんは、やや伝統的な福島県の女性にしては珍しく、公共の場で怒りを爆発させやすい。日常生活を考えると幸せは感じるものの、今後のことを長期的に考えると落ち込んでしまう。「今の生活は一時的なのです」と由香さんは言う。「朝外出して夜帰宅しますが、この生活は一時的なものです。まるで空中を漂っているみたいです」。
一家は、自分たちよりももっと苦しんでいる人々を知っている。近所の住民の大半が失業中であり、一日中自宅で過ごしている。謙一さんの元同僚の中には、放射能の被害を受ける恐れのない場所へと移住させた妻子と離れ離れになり、現場に残って作業を続けている人々もいる。
原発事故の発生直後、公衆衛生の専門家たちは放射能の危険性を懸念した。その後の分析によると、発電所付近の地域住民が必死にすばやく避難したため、健康への被害は比較的安全なレベルにとどまったという事実が判明した(「避難区域 」をご参照)。しかし、21万人の原発避難者が目に見えない放射能の脅威からくる不安、孤立感、そして恐怖に苦しんでおり、メンタルヘルスへの影響が危機にさらされている。

研究者や臨床医たちはこの問題を査定し軽減しようとしているものの、必要とされるサポートを日本政府が提供する意図や金銭的な余裕があるのかは不明である。加えて、政府に不信感を抱きメンタルヘルスについては口を閉ざしがちな避難者たちが、果たして助けを受け入れるのかも確かではない。こうした理由により、不安感、薬物乱用、またうつ病の発生率上昇に拍車がかかるのではないかと研究者たちは懸念している。
2万人近くの命を奪い何十億ドルもの経済的被害をもたらした津波を生き残った被災者に比べ、原発避難者を待ち受ける将来は厳しい。「津波の被災者たちの状況は改善しているようです。彼らのほうが、将来に対してより前向きな見方をしています」と述べるのは、両方の被災者グループの治療に携わってきた福島県立医科大学医学部の矢部博興である。原発避難者たちのうつ病は、「日増しにひどくなる一方」だ。
避難
福島県の各地には、果樹園、水田、そして漁村が広がっている。1970年代から80年代にかけ、東京に電力を供給する目的で2つの原子力発電所が建設され、周辺の住民たちは原子力発電を支持した。謙一さんは1994年に福島第一原子力発電所で働き始め、事故当時はメインテナンスなどを担当するエンジニアだった。由香さんは、看護師として病院に勤務していた。戸川夫妻は、9歳、12歳、15歳になる3人の子供たちと共に、住民の団結力が強い小さな浪江町にある4LDKのマンションに住んでいた。
一家の生活は、2011年3月11日14時46分に一変した。発電所の喫煙室にいた謙一さんは、地面が数分にわたり振動するのを感じた。事務所に走り、散らかった机や落下した天井を掻き分けて、免許証と車の鍵を手にした。車を走らせたはいいものの、地震と津波で橋や道路が破壊され発電所の外に出る道が塞がれていた。謙一さんは車を後にして、残り8キロの道のりを歩いて帰宅した。
関連ビデオ:福島のゴーストタウン
家族全員が無事であることは確認できたものの、発電所のことが心配だった。謙一さんは、発電所で緊急時に原子炉を冷却するシステムのメンテナンスを監督する立場にあった。もしこのシステムが起動しなければ、メルトダウンがすぐに発生し近郊の町に放射線が広がることを知っていたのだ。その晩は連発する余震のために何度も目覚め、テレビで報道を確認した。
謙一さんは不安を感じて当然だった。津波が炉心に冷却水を注入する装置を破壊していた。温度が上昇するにつれ、ウランペレットを大量に含んだ細長い燃料棒がゆがみ始めた。つまり、メルトダウンが既に発生していたのである。
翌朝、浪江町では避難を呼びかけるサイレンが鳴り響いた。戸川さん一家は北西に30キロほど離れた津島へ避難するよう勧告を受けた。車に乗り込んで車を走らせたが、道路はパニックに陥った住民たちであふれかえっており、別の避難所に移動せざるをえなかった。そして発電所内の非常用ディーゼル発電機も停止したことを聞いた謙一さんは、もう一度家族を車に押し込んで、津島の方向へと急いだ。パニックに陥りながらも、「逃げなければいけない」と考えていた。
道中で、東京電力の都内事務所で働いていた友人から携帯にメールが入った。第1号機の原子炉で爆発が発生し、福島県中に放射能が広がっているという知らせだった。一家は避難所を転々とし、発電所から北西に約40キロ離れた川俣町内の体育館にたどりついた。体育館の中は暗くて狭苦しかった。そこでは、堅材を繋ぎ合わせただけの空間を自宅として与えられた。それでも、一家は放射能の影響を大きく恐れていた。「放射能の影響についてはあまり知らなかったですし、川俣町が安全かどうかも分からなかったのです」と由香さんは言う。
日本では天災が頻発する。津波の発生直後、緊急通報受理機関は早急に活動を開始した。国中から医師や救急隊員が、捜索・救助作業の開始と救護のために東北地方太平洋沿岸へと向かった。拠点となったのは、福島県立医科大学である。地震発生から数週間にわたり、医科大学付属病院には重症の患者が搬送されると同時に、原子力災害における医療の最前線に立たされていた。医師たちは、ガイガーカウンターを使用して放射能に敏感に反応する甲状腺への被ばく量を測定した。また、高い被ばく量に苦しむ発電所の作業員数人への治療を行った。
最初の対応者
最初に対応した人々の中には、メンタルヘルスの専門家たちが含まれる。この事実は、国内におけるメンタルヘルスケアへの見方が変化していることを反映している。日本のメンタルヘルスケアは標準的ではあるものの最新だ。長年にわたり重度の精神疾患者のみを対象としており、従来うつ病などの慢性的な疾患にはほとんど注意が払われていなかった。しかし近年、日本医師会が医師に対してうつ病や自殺に関する指導を与えたり、政府は自殺防止対策を行なったりするなど、変化の兆しが見られる。
とはいうものの、いまだケアの質は低く、原発事故が発生する前の福島県でメンタルヘルスは重要視されていなかった。郊外や保守的な地域において、また寡黙な住民たちにとって心のケアに対する優先順位は低い。津波や原発事故の発生後、現地のメンタルヘルスサービスは限界に達する寸前だったと、矢部は述べる。

Credit: TORU YAMANAKA/AFP/Getty
事故発生後、県内で利用可能な資源の多くは重い精神疾患を患う人々に費やされた。そのため、矢部は抗精神病薬や抗けいれん薬を自身の車に詰め込み、多くの避難者が身を寄せる相馬市まで向かった。メンタルヘルスの専門家たちは遠方にある狭苦しい避難所を訪れたものの、重度の精神錯乱やPTSD患者のみの治療にあたる傾向があった。
何千人もの被災者がうろたえた医師やカウンセラーたちにより放任され、その中には戸川さん一家も含まれていた。狭苦しい避難所に住み始めた当初のことを今思い出すのは簡単ではないと由香さんは言う。不快な記憶ばかりが思い出される。「鎖につながれていない犬や猫のようでした」と由香さんは述べる。
外部からの助けはほとんどなく、避難所の住民たちは自ら頭を働かせ行動を開始した。看護師である由香さんは自分のスキルをボランティアとして提供し始めたが、3日間が経過すると怒りがこみ上げてきた。なぜ、被害者である自分が他の人たちを助けるために自分の時間をすべて費やさなければならないのか。由香さんは避難所外にある自家用車に鍵をかけ、「怒りを爆発させて泣き叫んだ」。
判断しにくい被害
避難者が順応しようともがいていたのと同様に、福島医大の医師や精神科医たちももがいていた。5月には緊急対応がほぼ完了し、病院は人々の放射線被ばく量を測定するという新しいミッションを与えられた。長崎大学の放射線医学者である山下俊一によれば、これは手ぎわを要する仕事だった。山下は、福島県民健康管理調査検討委員会の座長である。第一原子力発電所周辺の放射線モニターは地震と津波の被害を受けて壊れてしまったうえ、避難の渦中において個人が被ばくした期間や重度を測定するのは難しい。
数回の測定が行なわれ、大体の場合リスクは最小限であるという結果が出た。健康管理調査の最新測定結果によると、ほぼ全ての避難者の被ばく線量は最大でも25ミリシーベルト(mSv)と、非常に低い。広島・長崎の原爆で被爆量が100ミリシーベルト未満の被爆者のがん発症率が低かったことから、がん発症率増加には100ミリシーベルトが目安となっているが、それと比べても被災者の最大被ばく線量がはるかに下回っている。世界保健機関(WHO)が5月に発表した報告書では、浪江町を含む地域からの大半の避難者の被ばく線量は10から50ミリシーベルトであるという肯定的な発表があった。しかし、幼児の被ばく量をみるとまだ成長中の甲状腺にがんが発症する確率が増加する可能性があると述べている。
放射線の専門家たちよれば、低い被ばく量から健康への影響を予測するのは難しい。「がんのリスクが増加することはあるかもしれませんが、その可能性は極めて低いのです」と述べるのは、原爆生存者の研究を行なってきた統計学者の Dale Preston だ。「大規模な研究をすれば、統計的に有意な放射線リスクを観察できるチャンスはとても低いでしょう」。
これを踏まえ、県民健康管理調査では発症率を調べるため閉じたコホートを追跡しないという結論に至った。その代わり、希望する避難者を対象に甲状腺検査やその他の健康診断を提供している。「診断を行い収集されたデータを提示することにより、がん発症リスクが低いことを住民に伝えて安心してもらいたい」と山下は述べる。
メンタルヘルスは、調査の中で主な要素を占めている。2012年1月、研究者たちは避難者のストレスや不安感を調査するため、21万人の避難者全員にアンケートを配布した。精神保健研究所の鈴木友理子によれば、9万1千人以上の回答者が「非常に高い」レベルのストレスを感じていた。約15%の成人が過度のストレス(通常の5倍)を感じており、5人中1人に精神的トラウマの兆候がみられた。この数値は、アメリカ同時多発テロ事件の第一対応者と同様のレベルである。また、児童を対象とした調査結果は、日本人の平均に比べ2倍のストレスレベルを示した。

Credit: Osakabe Yasuo/Demotix/Corbis
避難者の中には、ストレスで極限状態に追いやられた人々もいる。その一人が飯舘村の大久保健二さんだ。良く晴れた11月の末日、大久保さんは発電所から北西に40キロ離れた飯舘村の人気のない通りでゴルフのスイングを練習している。発電所からの放射性プルームが村の上空を通過したため、村民は避難を余儀なくされたが、大久保さんは仮設住宅に耐え切れなかった。飲酒を始め、腹痛に苦しんだ。川俣町で部屋を借りた後、両親が捨てた家を占拠した。「ストレスから逃れるためだけに、帰ってきました」と言う。仕事も将来への見通しも無く、「前途が見えません」と、大久保さんは悲観する。
ハーバードメディカルスクール(マサチューセッツ州ボストン)の医療政策学部教授 Ronald Kessler によれば、これは大規模な災害が発生した後のパターンである。「短期間だと、人々はやる気を起します」と Kessler は言う。しかし、広大な被害や健康問題が元の生活に戻るのを妨げており、うつ病や不安感の原因となっている。「今回のように大規模なことが起こると、ただひたすら強い恐怖を感じるのです」と Kessler は述べる。「ある時点になると、ただ疲れてしまいます」。
Kessler は2005年にアメリカ合衆国を襲ったハリケーン・カトリーナからの避難者を対象に調査を行ない、不動産の損失と健康の懸念が不安感の主な原因であるという結果を得た。東北の津波の生存者の多くは自宅の再建が終了し元の生活に戻っているものの、原発避難者はいまだにそうした問題に直面している。それに加え、放射能への恐れからくる被害は厄介だ。「これは、感じることではないのです。何が起こったのか知らないにも関わらず、長期的なリスクがあると頭では分かっているのです」と、Preston は述べる。「恐ろしいことです」。
そうした恐怖が長期的にどのような影響を与えるかに関してはあまり明らかにされていない。特に、原発事故はそう頻繁には起こらないためだ。1986年のチェルノブイリ原発事故では、放射能への恐れが長期的な精神的損害を与えることが分かっている。事故から20年経過し幼少時代に避難を経験している人々は、同年代の同じ健康状態の人々に比べて身体的疾患を訴える頻度が高い。またそうした子供たちの母親がPTSDで苦しむ割合は一般の母親に比べて約2倍に上ると、ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校の精神科医である Evelyn Bromet は述べている。チェルノブイリ原発事故後、避難者の間ではうつ病の発症率が3倍も増加し、除去作業にあたった作業員の自殺率は一般の人に比べて1.5倍高いことが発見された。
福島の避難者に関しては、「健康に関する非常に大きな不安感がつのり、簡単には消えないでしょう」と Bromet は述べている。
懸念要素
矢部によると、「放射線恐怖症」が避難者の間で大きな問題となっている。ピュー研究所(ワシントン州)による福島県で生産された食品の安全性に関する世論調査によれば、政府や科学による安全性の裏付が行なわれているにも関わらず、日本人の76%が福島県産の食品が安全ではないと考えていることが分かった。また、政府が行なった健康管理調査の結果、高い放射線量が検出された避難者の数は非常に少なかったが、多くの人はこの結果を信じていない。
由香さんは、そうした懸念を共有する。由香さんと謙一さんは自分たちで知識を深め、定期健康診断と甲状腺検査の結果を受けていくぶん安心感を抱いている。また子供たちは、線量計を持ち歩いている。この線量計は、放射線データを収集し庶民の心配を軽減する目的で健康管理調査の一環で提供された。それでも、由香さんは将来子供たちががんにかかるかもしれないと考える。
現在、一家は現実的な悩みに頭を抱えている。現在入居中の仮設住宅には2014年8月まで居られるものの、その後はどうなるか分からないというのだ。「役人は、現在この問題に対応中で、避難者向けの公営住宅の建設を目指していると言っています。でも、どこにでしょう?何も明らかではありません」。由香さんは長期的な視線で将来のことを考え始めると、いつもひどく落ち込む。

Credit: Mai Nishiyama
福島県民健康管理調査に携わった科学者たちは、精神科医と看護師のチームを割り当て、メンタルヘルスのアンケートで高いストレスを感じていると応えた人に対してフォローアップの電話をかけている。しかし、アンケートに答えた成人は40%のみであり、最も深刻な影響を受けた人々は回答しなかったのだろうと、研究者たちは推測する。精神学者と話す機会があっても、たいてい避難者は5分から10分ほどしか電話口にとどまらない。「東北の人たちは閉鎖的です。個人的なことはあまり口にしません。初対面の人に対してはなおさらです」と矢部は述べる。
精神科医が問題を特定したところで、対処方法が明らかではない。戸川さん一家のように避難者の多くが、潜在的な問題に苦しんでいる。不安感やストレスのため入院や集中治療を必要とはしないものの、日常生活に影響を及ぼしている。矢部によれば、大災害の生存者への治療体制は確立されていない。
コミュニティとつながり家族を助けるため、矢部は予約なしで受診できるメンタルヘルスクリニックを福島県各地に設置することを提案中だ。鈴木は、受診者の多くにグループセラピーを受けてもらうのが今後の方向だろうと述べている。避難者の中で連帯感を高めていくことが助けになるだろうという声が大きいが、政府からの後押しはない。Brometの言葉を借りれば、仮説住宅は「線路のように疲れ果て」ている。「政府は、仮設住宅を建設する際、中央に遊び場を設けるか、住民が集える場所を設けてその周辺を囲うように設計することもできたのに、そうはしなかったのです」。
Kessler は、津波の生存者たちの悲しみは時と共に薄れていくものの、原発事故の避難者たちの抱える不安感、特に放射能に関する不安感が募る可能性を指摘している。「全てが落ち着いたときには、この問題が大きくなって深刻化していることでしょう」と、予測する。彼によれば、早めに解決策を講じるには今が最適の時期である。「今が絶好の機会なのです」。
健康管理調査でより大掛かりなプログラムを導入するには、資金が不足している。政府の予算では調査にかかる費用として一年間に30億円が割り当てられているが、現状ではその2倍の費用がかかっており、金銭的なプレッシャーは膨大である。こう述べるのは、福島県立医科大学の伝染病学者である安村誠司だ。21万人の避難者のうち、これまでにメンタルヘルスの専門家との直接カウンセリングを受けたのはわずか100人にとどまる。
少しずつではあるものの、戸川さん一家にとって物事は好転しつつある。子供たちは新しい学校を楽しんでいるようだし、謙一さんは2011年9月に自治体で新しい職に就き、近隣の住宅から放射能に汚染された土壌を取り除く作業に当たっている。「夫はあまりに残業してきたので、勤めている会社から休むようにといわれています」と由香さんは言う。由香さんは、地元のクリニックでパートタイムの看護師として働いている。時々由香さんが怒りを爆発させると同僚との間に緊張が生まれるものの、本人は自分の心のうちを話すことを楽しんでいる。「自分が言いたいことを言うのです」。
(翻訳:野沢里菜)