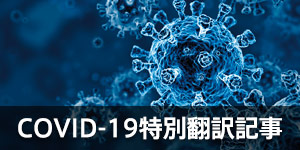地震学、再建への道 - すべてのデータを考え合わせる
原文:Nature 473, 146–148()|doi:10.1038/473146a|Rebuilding seismology: Integrate all available data
東日本大震災から約3か月半。5人の日本人地震学者が、今回の地震と津波から得た教訓について考察する。
5人の日本人地震学者の考察
鷺谷威:すべてのデータを考え合わせる|金森博雄:想定外の事態に備える|八木勇治:海底観察を強化|山田真澄:警報システムのさらなる改良|Jim Mori:より大きな揺れに耐えられるビルの設計
残念ながら日本政府は、このようなマグニチュード9クラスの地震が東北地方を襲う危険を予知することができなかった。だが、もし歴史的記録がもっとよく揃っていたなら、データ間の矛盾を見逃さなかったなら、大震災の危険性を十分警戒することができたかもしれない。
政府の地震調査研究推進本部が2002年に発表した、東北地方で沈み込み帯地震が発生する可能性に関する長期評価によれば、東北地方で30年以内にマグニチュード7.7~8.2の大地震が発生する確率は80~90%と推定されていた。しかし、400~500kmの範囲に影響を及ぼすマグニチュード9クラスの巨大地震が発生する可能性については、特に言及はなかった。長期評価部会のメンバーとして、私自身、このことを非常に遺憾に思っている。そこで今回、こうした危険性を見落としてしまった原因を考察したいと思う。

2002年の長期評価は、過去400年分のすべての歴史的地震記録の統計解析に基づいて行われた。しかし、3月に東北地方を襲った地震は、地震活動の適切な評価には400年という期間は短すぎることを露呈した。実は、日本の地質調査所の地質学者たちは、5年前から、西暦869年(貞観[じょうがん]11年)に仙台の沿岸部を水浸しにした津波についての研究報告を行ってきた。それは、今回の津波に匹敵する規模のものだったと思われる。しかし、こうした研究は最近のもので、まだ、予想される津波の規模を評価して対策を検討しようかという段階にあり、今回の震災には間に合わなかった。
われわれは、今回の経験から1つの重要な教訓を得た。それは、経験的手法により自然災害を評価したり予測したりする際には、かなり不確実な記録も含めて、利用可能な情報のすべてを考慮すべきであり、また確率に関係なく、あらゆる可能性を考慮しなければならないということである。
2002年の長期評価のもう1つの問題点は、検討対象のさまざまな観測データの間に明白な矛盾があることだった。過去10年間に行われたGPS(全地球測位システム)調査は、日本海溝に沿ったプレート境界がほぼ完全に固着して、すべっていないことを示唆していた1,2。しかし、何年も前から、日本海溝では、プレート運動に占める大地震の際の累積的なすべり量の割合(サイスミック・カップリング係数)が約30%にしかならないことがわかっていた。つまり、プレート運動の残りの70%がどうなっているのかについては、説明がつかなかったのだ。
われわれ日本の地震学者たちはこの矛盾に気付いていたが、これほど破滅的な意味を持つとは深刻に考えてはいなかった。2001年、京都大学の川崎一朗(かわさき いちろう)は、日本海溝の北部については、プレート運動のかなりの部分が「余効すべり」、すなわち、大地震が終わってから発生するすべりや、その他の非地震性の断層運動により説明できると発表した3。しかしながら、今回のマグニチュード9.0の地震の主な震源となった南部における矛盾は残った。
今回、得られた第二の教訓は、こうした矛盾するデータを見過ごしてはならず、観測データからの情報を、異なる時間・空間スケールに結びつけて検討するよう努めなければならないということだ。
地球科学は多くの分野にわたっている。日本の地震学コミュニティーは、地震学、測地学、地形学、地質学データのすべてを再検討して、現在の評価に欠けている情報を見つけ出し、矛盾があれば解消する必要があるのだ。
(翻訳:三枝小夜子)
本記事は、Nature ダイジェスト 2011年7月号に掲載されています。